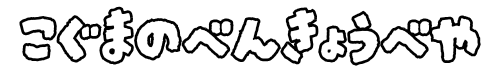最高裁第三小法廷 昭和60年(1985年) 4月23日
本記事の参照:裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
kuma
文中の下線(アンダーライン)は、
判決文に下線が引いてある部分です。
上告代理人小倉隆志の上告理由第一点について
所論の点に関する原判決の説示の趣旨は、労働条件の決定等に関して使用者のとつた労働組合ないしは
労働者に不利益な特定の行為が使用者の自由に属する範囲の行為であるか、それとも労働組合活動に対して不当な影響力を行使するものとして不当労働行為と目すべきものであるかを判断するにあたつては、単に問題となつている行為の外形や表面上の理由のみを取り上げてこれを表面的、抽象的に観察するだけでは足りず、使用者が従来とつてきた態度、当該行為がされるに至つた経緯、それをめぐる使用者と労働者ないしは労働組合との折衝の内容及び態様、右行為が当該企業ないし職場における労使関係上有する意味、これが労働組合活動に及ぼすべき影響等諸般の事情を考察し、これらとの関連において当該行為の有する意味や性格を的確に洞察、把握したうえで判断を下すことが必要であるとの見地から、右のような使用者の行為について不当労働行為の成否が問題となつている救済命令取消訴訟において、裁判所が右不当労働行為の成否を判断するについては、単に労働委員会の作成した命令書記載の理由のみに即してその当否を論ずべきものではなく、その判断の基礎となつたと考えられる背景事情等にも十分思いをめぐらしたうえで総合的な視野に立つて結論を下すべきであるとの認定、判断の心構えを述べているものであつて、所論のごとく不当労働行為の成否について労働委員会に裁量権があり、これについて裁判所が立ち入つた判断をすべきでない、との趣旨を述べたものでないことは、判文に徴して明らかである。
原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。
論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
同第二点及び第三点について
一 まず、所論は、「従業員の時間外及び休日労働について、申立人支部に所属する者をそうでない者より不利益に取り扱つてはならない。」という本件不当労働行為救済申立の趣旨は、製造部門については、参加人C1工業支部(以下「支部」という。)所属組合員にも後記四1(一)のような計画残業に服せしめよということにほかならないとの見解を前提としたうえで、そうである以上、本件救済申立を認容するためには、支部所属組合員に計画残業に服する意思の存在すること、支部が上告人会社に計画残業に服せしめるべきことを要求したこと、上告人会社がこの要求を拒否したことの三つの要件が必要であるところ、本件においては、支部所属組合員が計画残業に服する意思を有することはなんら主張立証されず、かえつて、支部及びその所属組合員が計画残業に反対し、これに服することを拒否していることは明らかであるから、本件救済申立は棄却されるべきものであるにもかかわらず、これと異なる判断をして本件再審査命令を維持した原判決には、審理不尽、理由不備、理由齟齬の違法及び憲法六五条、七六条違背がある、というものと解される。
しかしながら、不当労働行為救済申立制度は、労働問題を取り扱う専門機関として設けられた行政委員会たる労働委員会が、一定の救済利益を有すると認められる者の申立に基づき、申立人が不当労働行為を構成するとして主張した具体的事実の存否及びその事実が不当労働行為に該当するか否かを審理判断し、それが肯定される場合には、その裁量により、当該具体的事案に即して、当該不当労働行為による侵害状態の除去、是正のために必要と認めた作為、不作為の措置を命ずることによつて、労働者の団結権を保護し、正常な集団的労使関係秩序の回復、確保を図ろ
うとするものである。
したがつて、申立人が救済命令を申し立てるにあたり申立書に記載すべきものとされる「請求する救済の内容」(労働委員会規則三二条二項四号)は、労働委員会が不当労働行為の成立を認めたうえで、しかるのちこれに対する救済を命ずる場合に、その命ずべき救済の内容に関する労働委員会の裁量の範囲を画する意味を持つことがあるにとどまり、不当労働行為救済申立事件における労働委員会の審理が右「請求する救済の内容」の当否についての判断を直接の目的として行われるというものではない。
これと異なる前提に立つ論旨は、失当である。
のみならず、後記のような原審の適法に確定した本件救済申立の経緯に関する事実関係によれば、本件不当労働行為救済申立は、所論のように支部所属組合員にも計画残業に服せしめよというような限定された救済を求める趣旨でされたものでないことはおのずから明らかである。論旨は、本件救済申立の趣旨について、右と異なる解釈のもとに原判決を論難するものであって、採用することができない。
二 ところで、所論は、支部所属組合員に計画残業に服する意思がなく、あるいは支部が計画残業に反対し、これに服することを拒否している以上、その所属組合員に残業を命じない会社の措置につき不当労働行為は成立しないと主張し、その見地から、本件につき不当労働行為の成立を認めた原判決の不当をいう趣旨であるとも解せられる。
そこで、以下これについて判断する。
1 原審の適法に確定するところによれば、本件不当労働行為救済申立の経緯及
びその後本件再審査命令が発せられるまでの団体交渉の経緯は、次のとおりである。
kuma
事実確認が続きます。
すなわち、昭和四一年八月一日に旧D自動車工業株式会社(以下「旧D」という。)を吸収合併した上告人会社には、E自動車労働組合(以下「E労組」という。)と支部との二つの労働組合が併存し、支部はかねてから深夜勤務反対等の情宣活動を行つていたところ、昭和四二年二月から、上告人会社は、支部に対してなんらの申入れ等を行うことなく、E労組とのみ協議しただけで、上告人会社が従来その工場の製造部門で実施してきた昼夜二交替の勤務体制(いわゆるE型交替制)及び計画残業方式を旧Dの工場の製造部門にも導入し、それ以来、同部門においては、E労組所属の組合員のみを右交替制勤務に組み入れ、かつ、同組合員に対し恒常的に計画残業と称する一日一、二時間の時間外勤務及び月一回程度の休日勤務をさせてきたが、支部所属の組合員に対しては、一方的に早番(右交替制における昼間勤務のこと。これに対し、夜間勤務を遅番という。)のみの勤務に組み入れ、かつ、残業(時間外勤務及び休日勤務をいう。以下同じ。)を一切命じないとの措置をとつた。
また、交替制勤務のない間接部門(事務・技術部門をいう。以下同じ。)においても、E労組所属の組合員に対しては、同労組との協定に基づき、業務の必要に応じて一日四時間、一か月五〇時間の範囲内で残業を命じたが、支部所属の組合員に対しては右同月以降全く残業を命じなくなつた。支部は、当初は残業に関する右会社の措置につき抗議したり、是正を要求したりすることはなかったが、同年六月、支部所属組合員にも残業をさせるよう上告人会社に申し入れ、同月三日以降同年一一月二八日までの間の数回の団体交渉において右残業問題を取り上げ、支部所属組合員を残業から除外しているのは上告人会社の方針かどうか、その理由は何か、などの点を追及した。
これに対し、会社側は、右の点は会社の方針ではないとしたうえ、「残業をさせないのは現場職制との信頼関係の問題だ。支部が残業反対をとなえ、必要なときに残業をやつてもらえないということでは各職制も残業を頼めなくなるだろう。」等の趣旨のことを述べ、これに対して支部は、「支部が反対しているのは強制残業についてであつて、三六協定に基づく残業には従来から協力してきた。」等の趣旨のことを述べるなどの応酬で推移し、進展をみなかつた。
そこで、支部は、同年一二月一五日、上告人会社に対して、夜間勤務に応ずる条件として、
① 週五日制とすること、
② 昼間よりベルトコンベアのスピードを落とすこと、
③ 夜勤手当を増額することなど
を要求して団体交渉を申し入れるとともに、同月二七日、残業問題をめぐる紛争について東京都地方労働委員会(以下「都労委」という。)に斡旋を申請した。
昭和四三年一月二六日、都労委の斡旋員の勧告に基づいて行われることになつた右残業問題に関する支部との団体交渉の席上において、上告人会社は、初めて、支部に対し、
(1) E型交替制と計画残業は組み合わされて一体をなすものであるとして、その内容及び手当等について具体的な説明を行うとともに、
(2) E労組は右のような勤務体制を承認し、これに服しているのであるから、支部もこれと同じ態度をとらない限り支部所属組合員を残業に組み入れることはできない、との態度を示し、また、
(3) 夜間勤務のない間接部門においては、各職場の職制がその判断によつて残業をさせるが、各職制が支部所属の組合員に残業をさせないのは、一般に同組合員がE労組所属の組合員と同じ勤務体制に服する姿勢を示さないからであると考えられるとの趣旨を述べた。
そして、上告人会社は、支部が夜間勤務に応ずる条件として提示した前記諸要求についてはこれを拒否した。
これに対し、支部は、残業協定と夜間勤務協定とは別個の問題であり、夜間勤務については原則的には反対する旨を述べ、現在の条件のままでは夜間勤務には応じられないとし、結局交渉はもの別れに終つた。
そこで、同年二月二二日、支部は、参加人C2組合(以下「C2」という。)及び同C3とともに、上告人会社が支部所属組合員に対し残業を命じないことは、支部所属の組合員であるというだけの理由でE労組所属の組合員と差別し、支部所属組合員に経済的不利益を与えようとする不当労働行為であるとして、都労委に対し、「上告人会社は、従業員の残
業について、支部に所属する者をそうでない者よりも不利益に取り扱つてはならない」旨の本件救済申立をした。
右申立に対し、都労委は、昭和四六年五月二五日付で、支部所属組合員に残業を命じない上告人会社の措置につき不当労働行為の成立を認め、「上告人会社は、支部所属の組合員に対し時間外勤務(休日勤務を含む)を命ずるにあたつて同支部組合員であることを理由として他の労働組合員と差別して取り扱つてはならない。」旨の救済命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。
そこで、上告人会社は、被上告人に再審査の申立をするとともに、同年六月一八日から翌四七年四月一八日までの間、合計八回にわたつて支部と右残業問題に関する団体交渉を行つた。
右交渉において、上告人会社は、支部に対し、製造部門についてはE労組所属の組合員と同様に交替制と計画残業に服すべき旨を主張し、また、右勤務体制のとられていない間接部門については、以後残業を命ずることにするのでこれに服するよう申し入れた。
これに対して、支部は、交替制に伴う夜間勤務には原則的に反対である旨の従来の立場を主張し、また、間接部門については、支部所属の組合員はほとんど残業を必要としないような作業や質の低い作業に就かされているので、その改善が先決であり、その点が解決されない限り会社側の提案は受け入れることができない旨主張した。
このようにして、製造部門、間接部門とも残業問題について合意をみるに至らず、上告人会社は支部所属組合員に残業を命じないとする措置を継続していたところ、被上告人は、昭和四八年三月一九日付で再審査申立を棄却する旨の本件再審査命令を発した。
kuma
事実確認はここまで。
2 以上によれば、本件救済申立事件における不当労働行為成否の要点は、上告人会社内にはE労組と支部という二つの労働組合が併存しているところ、上告人会社が先にE労組との間に締結した労働協約に基づき実施している勤務体制(いわゆるE型交替制勤務)及び右勤務体制の一環としてこれに組み合わされている計画残業に支部がかねてから反対し、残業に関する団体交渉が行われたのちにおいても、支部は、E労組所属の組合員が服しているのと同一の労働条件による残業には服し難いとして、これについての協定を締結することを拒否したという状況のもとにおいて、上告人会社が支部所属組合員に対して一切の残業を命じないとの措置をとり、これを維持していることが労働組合法(以下「労組法」という。)七条三号の不当労働行為を構成するかどうか、という点にある。
三 そこで考えるに、労組法のもとにおいて、同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、各組合は、その組織人員の多少にかかわらず、それぞれ全く独自に使用者との間に労働条件等について団体交渉を行い、その自由な意思決定に基づき労働協約を締結し、あるいはその締結を拒否する権利を有するのであるから、併存する組合の一方は使用者との間に一定の労働条件のもとで残業することについて協約を締結したが、他方の組合はより有利な労働条件を主張し、右と同一の労働条件のもとで残業をすることについて反対の態度をとつたため、残業に関して協定締結に至らず、その結果、右後者の組合員が使用者から残業を命ぜられず、前者の組合員との間に残業に関し取扱いに差異を生ずることになつたとしても、それは、ひつきよう、使用者と労働組合との間の自由な取引の場において各組合が異なる方針ないし状況判断に基づいて選択した結果が異なるにすぎないものというべきであつて、この問題を一般的、抽象的に論ずる限りにおいては、残業について両組合員間に右のような取扱上の差異を生ずるような措置をとつた会社の行為につき不当労働行為の問題は生じないものといわなければならない。
しかしながら、右の議論は、あくまでも当該団体交渉の結果について、組合がその自由な意思決定に基づいて選択したものとみられうべき状況のあることが前提であることはいうまでもない(この場合、当該組合の組織が小さく、交渉力が弱いために、結果として使用者に対し組合の要求を通すことができなかつたとしても、それをもつて自由な意思決定によらないものであるとすることはできない。)。
そして、右のような団体交渉における組合の自由な意思決定を実質的に担保するために、労組法は使用者に対し、労働組合の団結力に不当な影響を及ぼすような妨害行為を行うことを不当労働行為として禁止すると同時に、かかる不当労働行為から労働組合と労働者を救済することとしているのである。
右のように、複数組合併存下にあつては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによつて差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。
ところで、中立的態度の保持といい、平等取扱いといつても、現実の問題として、併存する組合間の組織人員に大きな開きがある場合、各組合の使用者に対する交渉力、すなわちその団結行動の持つ影響力に大小の差異が生ずるのは当然であり、この点を直視するならば、使用者が各組合との団体交渉においてその交渉相手の持つ現実の交渉力に対応してその態度を決することを是認しなければならないものであつて、団結力の小さい組合が団体交渉において使用者側の力に押し切られることがあつたとしても、そのこと自体に法的な問題が生ずるものではない。
すなわち、同一企業内に圧倒的多数の従業員を組合員として擁する多数派組合と、極く少数の従業員を組合員として擁するにすぎない少数派組合とが併存する場合、その企業における勤務体制に関しては、一般に、職場全体を通じて均等な労働条件による統一的な勤務体制がとられることが望ましいものであることはいうまでもないところであり、使用者はいずれの組合とも十分協議を尽すべきであるが、事実として、多数派組合の交渉力の方が使用者の意思決定に大きな影響力をもたらすことは否定できないところであるから、使用者としてかかる労使間の問題を処理するにあたつて、いきおい右多数派組合との交渉及びその結果に重点を置くようになるのは自然のことというべきであり、このような使用者の態度を一概に不当とすることはできない。
労働条件の適用について圧倒的多数の労働者の団結権及びその意思を重視する姿勢は労組法の規定にもこれを窺うことができるのである(同法一七条参照)。
したがつて、例えば、使用者において複数の併存組合に対し、ほぼ同一時期に同一内容の労働条件についての提示を行い、それぞれに団体交渉を行った結果、従業員の圧倒的多数を擁する組合との間に一定の条件で合意が成立するに至つたが、少数派組合との間では意見の対立点がなお大きいという場合に、使用者が、右多数派組合との間で合意に達した労働条件で少数派組合とも妥結しようとするのは自然の成り行きというべきであつて、少数派組合に対し右条件を受諾するよう求め、これをもつて譲歩の限度とする強い態度を示したとしても、そのことから直ちに使用者の交渉態度に非難すべきものがあるとすることはできない。
そして、このような場合に、労使双方があくまで自己の条件に固執したため労働協約が締結されず、これにより少
数派組合の組合員が協約の成立を前提としてとらるべき措置の対象から除外され、このことが同組合員に経済的不利益の結果をもたらし、ひいて組合員の減少の原因となり、組合内部の動揺やその団結力の低下を招くに至つたとしても、それは、当該組合自身の意思決定に基づく結果にすぎず、ひつきよう、組合幹部の指導方針ないし状況判断の誤りに帰すべき問題である。
このような場合に、使用者において、先に多数派組合と妥結した線以上の譲歩をしないことが、少数派組合の主張や従来の運動路線からみて妥結拒否の回答をもたらし、協約不締結の状態が続くことにより、その所属組合員に経済的な打撃を与え、ひいては当該組合内部の動揺や組合員の退職、脱退による組織の弱体化が生ずるに至るであろうことを予測することは極めて容易なことであるとしても、そうであるからといつて、使用者が少数派組合に対し譲歩をしないことが、同組合の弱体化の計算ないし企図に基づくものであると短絡的な推断をすることの許されないものであることはいうまでもない。
そうでなければ、使用者は少数派組合の要求に譲歩しない限り一般的に不当労働行為意思が推定されるという不当な結果となるであろう。
以上のように、複数組合併存下においては、使用者に各組合との対応に関して平等取扱い、中立義務が課せられているとしても、各組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることが右義務に反するものとみなさるべきではない。
したがつて、以上の諸点を十分考慮に入れたうえで不当労働行為の成否を判定しなければならないものであるが、団体交渉の場面においてみるならば、合理的、合目的的な取引活動とみられうべき使用者の態度であつても、当該交渉事項については既に当該組合に対する団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となつて行われた行為があり、当該団体交渉がそのような既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる特段の事情がある場合には、右団体交渉の結果としてとられている使用者の行為についても労組法七条三号の不当労働行為が成立するものと解するのが相当である。
そして、右のような不当労働行為の成否を判断するにあたつては、単に、団体交渉において提示された妥結条件の内容やその条件と交渉事項との関連性、ないしその条件に固執することの合理性についてのみ検討するのではなく、当該団体交渉事項がどのようないきさつで発生したものかその原因及び背景事情、ないしこれが当該労使関係において持つ意味、右交渉事項に係る問題が発生したのちにこれをめぐつて双方がとつてきた態度等の一切の事情を総合勘案して、当該団体交渉における使用者の態度につき不当労働行為意思の有無を判定しなければならない。
四 そこで、以上の見地に立つて、上告人会社が、支部において上告人会社の提示する交替制勤務及び計画残業方式に服することに合意しないことのゆえをもつて支部所属組合員に対しては一切の残業を命じないとしていることについての不当労働行為の成否について考えるに、原審の適法に確定した事実関係によれば、以下の諸点を指摘することができる。
1(一) 上告人会社が合併後の旧Dの製造部門に導入した前記交替制と計画残業とは、従来から上告人会社の他の工場において採用してきたものであり、所与の生産設備と労働力を十二分に活用して生産効率を挙げることを目的として考え出された勤務体制であつて、両者は密接な関連性を有するものである。
そして、計画残業とは、毎月の生産計画達成に必要とされる従業員一人あたりの月間残業時間を、従来の残業就労率を見込んで職場単位に算出し、これを就労日に割り振るなどして、従業員を計画的に日々必要時間数だけ残業に服させようとするものであるから、製造部門、特にベルトコンベアー作業に従事する従業員中に計画残業に服さない者が出た場合には、他の従業員を補充して作業にあたらせなければならず、この補充体制を整えるためにはかなりの手数を要し、したがつて、計画残業に服することの不確実な従業員を右作業に組み入れるときには、作業の円滑な遂行が阻害されることになる。
(二) そこで、上告人会社は、昭和四三年一月二六日の団体交渉において、支部に対し、製造部門においては、上告人会社がE労組との労働協約に基づき実施しているのと同一の労働条件のもとに支部所属組合員が計画残業に服することについて合意することを強く主張し、支部が右会社の提案に同意しない限りその組合員に対する残業組入れを全面的に拒否する旨の態度を示したものであるが、このような上告人会社の主張については、合理的理由があるものといわざるをえない。
けだし、支部が計画残業に同意する旨を表明しない状況のもとでは、個々の組合員が計画残業に服するか否か予測し難いにもかかわらずその全員を計画残業に組み入れなければならず(個々の組合員によつて異なる取扱いをすれば、差別取扱い、組合切りくずしの非難を受けることになろう。)、この場合に、組合員が右計画残業に非協力の態度を取れば、その補充体制を整えるために相当の手数を要するとともに、あらかじめこれに備えるとすれば上告人会社に余分の負担を与えることになると考えられるからである。
また、前記交替制及び計画残業は、上告人会社が合併前からその工場で採用してきた制度であり、合併後これを旧Dの工場に導入するについて圧倒的多数の労働者を組織する組合の同意を得られたものであつて、かつ、その制度自体の合理性を否定することができないものであるうえに、同一の事業場においては全従業員が統一的な勤務体制により就労することによつて効率的な作業運営が図られるものであることに鑑みると、上告人会社が前記のような態度で支部との交渉に臨んだことについては、この限りにおいてこれを不当として非難することはできないものと考えられる。
(三) しかしながら、右団体交渉における支部に対する上告人会社の要求が一見合理的かつ正当性を承認しうるような面を備えているとしても、その真の決定的動機が少数派組合である支部に対する団結権否認ないしその弱体化にあり、本件の残業問題に関する団体交渉が右の意図に基づく既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められるときは、これに対する会社の行為はこれを全体的にみて支配介入にあたるものといわなければならない。
2(一) ところで、上告人会社と旧Dとの合併を前にして、旧Dにおける唯一の労働組合であつた支部は、右合併及び合併後のE労組との組織統一等をめぐつて態度決定を迫られたが、支部執行部及びこれを支持する少数の組合員は旧Dにおける既得の労働条件が低下するおそれがあるなどとして合併に対し消極的であつたところ、結局、旧D従業員約七八〇〇名中約七五〇〇名を擁していた支部の組合員のうち後記一五二名を除くその余の組合員が、支部をC2から脱退させ、合併後はE労組に統合することを予定して、支部の名称をD自動車工業労働組合(以下「D自工組合」という。)と改称するという動きに出た結果、C2に所属する支部は僅か一五二名の組合員を擁する少数派組合となつてしまつたものである。
(二) 上告人会社及び合併前の旧Dは、右のように、支部が会社合併及び労働組合の組織統一等をめぐる組合内部の意見の対立により大多数の組合員がC2を脱退してD自工組合を結成し、支部は僅か一五二名の少数派組合となつた一連の過程において、合併を成功させようとする立場から、おのずからE労組やこれに同調する支部内の動きに対して好意的であり、前記多数派によるC2からの支部の脱退及び組合の名称をD自工組合と改称した旨の通告を受けた時点においてC2に所属する支部は消滅したものとする態度をとり、前記残存組合員らによる団体交渉の申入れを拒否し、合併後の労働条件についてD自工組合とのみ協定を結び、合併後も右と同様の態度をとつた。
そして、この間に会社側がとつた措置ないし態度については、C2や支部は、(1) 旧Dが、支部の組合員らに対するE労組の働きかけにつき、側面援助を行つているものであるとして、(2) また、前記多数派によるC2脱退後、残存組合員からなる支部に対して団体交渉を拒否しているとして、それぞれ都労委に不当労働行為の救済申立を行い、さらに、(3) 合併後に上告人会社が行つた支部所属組合員六名の配置転換につき、労組法七条一号の不当労働行為であるとして都労委に救済申立をする等の対抗措置をとり、これらに対し、次のような救済命令が発せられた経緯がある。すなわち、右(1)申立に対しては、昭和四一年七月二六日付で、(ア) 旧Dは、工場長、課長をして支部の組合員に対してC2の支持を弱めるような言動をなさしめたり、また、係長、班長が係員に対し就業時間中に同旨の説得活動を行うことを放置してはならない、(イ) 旧Dは、C2の組合員以外の者がC2の支持を弱めるような活動をするにあたつて、会社の会議室や食堂を利用させるなどの特別の便宜を供与してはならない、との一部救済命令が発せられ、同命令は確定した。
また、(2)の申立に対しては、同年七月一二日付で、旧Dは支部からの申入れに係る団体交渉に応じなければならない、との救済命令が発せられ、これに対する旧Dからの再審査申立に対しても、同年一一月二六日付で、合併後の上告人会社を名宛人として、右初審命令を維持する命令が発せられ、同命令は確定した。
さらに、(3) の申立に対しては、昭和四六年四月六日付で、六名の原職ないし原職相当職への復帰を内容とする救済命令が発せられ、これについては、再審査手続の段階で原職復帰の線に沿う和解で解決した。
3(一) ところで、上告人会社は、昭和四二年二月から前記交替制と計画残業を旧Dの製造部門に導入したものであるが、かかる労働条件の変更を伴う勤務体制を事業場に導入するについて、E労組とのみ協議してその導入を決定し、支部とはなんらの協議も行うことなく、一方的に支部所属組合員を昼間勤務にのみ配置し、かつ、右導入以後同組合員につき一切の残業への組入れをしなかつた。
このことに正当な理由があつたのかどうかを検討する必要がある。
前記のとおり、支部に対する団体交渉の拒否について、これを不当労働行為であるとして団体交渉に応ずべきことを命ずる初審命令を維持した再審査命令があつたのは昭和四一年一一月二六日付であり、支部は、右救済命令の確定と前後して上告人会社に団体交渉の申入れをし、昭和四二年一月以降に団体交渉の日時、場所、出席者等、団体交渉のルールの設定につき予備折衝を経たのち、同年三月二二日を第一回として正式の団体交渉を持つに至つた。
右の経過からすると、昭和四二年一月下旬の段階で、上告人会社が支部を独立の労働組合と認めてこれに対し右交替制及び計画残業の導入につき会社側の意向を提案すること自体に格別の困難があつたとはみられない。
(二) 確かに、右勤務体制は上告人会社が合併前からその工場で採用してきた制度であり、合併後これを旧Dの工場にも導入する方針については、既に合併前にD自工組合との間に基本協定が締結されていたことである(ちなみに、合併前の旧Dの製造部門においても、二直二交替制ないし二直三交替制の勤務体制により深夜勤務が実施されていた。ただし、右の夜間勤務者に対してはほとんど残業を課すことはなく、昼間勤務者に対しては多少の残業を課すことがあつたが、残業を命ずるにあたつては、現場上司が各部下に個別的に残業に服するかどうかを確かめ、残業応諾者のみで不足するときには他の部署から応援を求めるなどして所要人員を確保し、これらの者に対して業務命令を出すという方法の、いわゆるD方式による残業が行われていた。)。
また、支部としても、会社の合併をめぐり労働組合としての態度決定をするについては、当然上告人会社が従来からその工場で実施してきた前記交替制及び計画残業の実情を調査していたものと考えられるのであり、合併後これが旧Dの工場に導入されたことについても、全く未知の制度が突然導入されたというのとは異なり、むしろ合併後その導入にいかに対応すべきかは既定の問題であつたといいうる。
そして、支部は、上告人会社が合併後旧Dの工場にE型交替制及び計画残業を導入する前から深夜勤務反対等の旨を情宣活動等において表明し、また、右導入後支部所属組合員が計画残業に組み入れられなかつたことについて、当初これを差別的取扱いとして抗議したり、是正を要求したりすることもなかつた。
そればかりか、支部は、昭和四二年三月から六月ころまでの間、春闘やメーデー参加等に際して、「会社の残業政策を粉砕しよう」、「労働条件を合併前に戻せ」、「深夜勤務の強化、夜勤の早出、隔週夜勤反対」、「残業、公出……の強制反対」、「強制残業、深夜勤務はすぐやめよ」、「残業は自由意思でやらせろ」等の記載のあるビラを配布していたのであつて、このような事実からすると、支部は、上告人会社の採用している右勤務体制を知つたうえで、計画残業を強制残業であるとしてあえてこれに反対しているものと会社側が受け取ったとしても当然とみられる活動を展開していたのである。
また、その後の団体交渉の経過をみても、支部はE労組所属の組合員と同一の労働条件の下での交替制及び計画残業に服することを拒否し続けたことが明らかであり、その立場は会社側の説得の余地に乏しかつたことも否定することはできない。
(三) しかし、そうであるからといつて、支部の側に団体交渉の姿勢がなかつたといえない以上、右のような事情をもつて、上告人会社が前記交替制及び計画残業を旧Dの製造部門に導入するについて支部となんらの協議も行わず、かつ、右導入以後支部所属組合員につき一切の残業から排除したことを正当ならしめる事由と解することはできない。
ことがらは、労働条件の中でも基本的な事項である勤務体制及び労働時間をどのように協定するかという問題である。現に企業内にE労組とは別個独立の労働組合が存在していることを認めざるをえない状況にありながら、使用者が右労働条件について労働組合の一方とのみ協議し、他方の組合にはなんらの提案すら行わないというのは、後者の組合についてはその存在を無視して企業運営を図ろうとする意図のあらわれとみられてもやむをえないところである。
これは、同年六月の六回目の支部との団体交渉において支部から初めて会社の支部所属組合員に対する残業に関する措置の問題が提起されたのち、同年中において会社側の示した交渉態度が、その後示した態度とは裏腹に、支部所属組合員を残業から除外しているのは会社の方針ではなく、現場職制の同組合員に対する不信感に由来するものであると述べるなど、専ら抽象的、水掛け論的論議に終始して、交替制及び計画残業の内容やその必要性、妥当性につきそれなりの説明をして支部の説得を試み、その同意をとりつけるための努力を払つた形跡がみられないという点にも窺われるところであり、以上のところからすると、上告人会社は、支部が前記のような情宣活動等を行つていたことをいわば逆手に取つて、誠意をもつて交渉する態度を示さなかつたものとみられるのである。
そして、上告人会社による右勤務体制及び計画残業についての具体的説明並びに支部がこの勤務体制に服することに同意しない限り残業に組み入れることができない旨の態度の表明は、この問題について支部が都労委に斡旋申請をし、その斡旋員の指示によつて開かれた昭和四三年一月二六日の団体交渉の際に初めてされたのである。
(四) さらに、本件初審命令後の団体交渉においても、上告人会社は、支部所属組合員を残業に就かせない状態を継続しつつ、E労組所属の組合員と同一の勤務体制に服することを残業組入れの前提条件としたものであつて、その交渉態度に特段の変化があつたとはみられない。
4(一) 間接部門においては、遅番勤務がなく、したがつて同部門における残業を含む作業割当ては前記交替制に対する支部としての賛否の問題とはかかわりかないにもかかわらず、上告人会社は同部門に勤務する支部所属組合員に対しても昭和四二年二月以降一切残業を命じていない。そして、上告人会社が間接部門に勤務する支部所属組合員に対し一切残業を命じなくなつた理由として本件救済申立前に支部との団体交渉において主張したところは、要するに支部所属組合員に対する職制の信頼がないからであろうというようなものでしかない。
(二) ところで、間接部門においては、交替制や計画残業を実施しているわけではなく、各職制が必要に応じて残業をさせるという方式が採られており、支部も三六協定に基づく残業には応ずる旨を表明していたのであるから(なお、上告人会社における圧倒的多数派組合であるE労組との間に三六協定が締結されていたこと及び上告人会社の就業規則に業務上必要がある場合に会社が残業を命じうる旨の定めがあることは、記録上明らかである。)、上告人会社が同部門の支部所属組合員に残業を命じるについては同支部と更に特段の協定、協約を締結しなければならな
いというものではなく、上告人会社が支部所属組合員に対して一方的に残業を命ずることができたのである。
もとより、一般的にいえば従業員に残業を命ずることが会社の義務であるわけではない。
しかし、残業手当が従業員の賃金に対して相当の比率を占めているという労働事情のもとにおいては、長期間継続して残業を命ぜられないことは従業員にとつて経済的に大きな打撃となるものであるから、同一部門における併存組合のいずれの組合員に対しても残業を命ずることができる場合において、一方の組合員に対しては一切残業を命じないという取扱上の差異を設けるについては、そうすることに合理的な理由が肯定されない限り、その取扱いは一方の組合員であるがゆえの差別的不利益取扱いであるといわなければならず、同時に、それは、同組合員を経済的に圧迫することにより組合内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を図るものとして、その所属組合に対する支配介入を構成するものというべきである。
そして、支部が、製造部門において交替制及び計画残業に反対の態度をとり、E労組所属の組合員と同一の労働条件のもとでの右勤務体制及び残業に服することを拒否しているからといつて、間接部門における支部所属の組合員についてまで一切残業を命じないとするのは、これを製造部門に関する残業の条件について支部との団体交渉が始まつた以後は、これとの交渉を有利にするための取引の手段としたものとしても、右交渉の目的との間の合理的関連性を欠くものといわざるをえず、もとより右団体交渉の以前においては、これを正当としうるなんらの合理的理由も
見出すことはできない。
(三) 要するに、間接部門におけるこの問題に関する会社の態度を通してみるならば、上告人会社には、残業に関し支部所属の組合員をその組合員であるというだけの理由でE労組所属の組合員と差別して取り扱い、支部所属組合員を経済的に不利益な状態に置くことによりその組織の動揺ないし弱体化を図つたものとみざるをえないのである。
そして、支部は、製造部門と間接部門の二つの組織からなるわけのものではなく、統一組織体であることを考えれば、上告人会社が支部所属組合員に対してとつた残業問題に関する措置の真の意図が製造部門と間接部門とで異なつていたものと考えるのは不自然さを免れない。
5 そこで、右の4の点に前記2、3の点を合わせ考えるならば、本件残業問題に関し、上告人会社が支部所属組合員に対し残業を一切命じないとする既成事実のうえで支部との団体交渉において誠意をもつて交渉せず、支部との間に残業に関する協定が成立しないことを理由として支部所属組合員に依然残業を命じないとしていることの主たる動機・原因は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものであつたと推断されてもやむをえないものである。
五 したがつて、以上と同旨の見地に立ち、団体交渉の結果として措置を継続しているかにみえる製造部門における支部所属組合員の残業組み入れ拒否につき、労組法七条三号の不当労働行為が成立するものとした原審の判断は、これを是認するに足り、
原判決に所論の違法はない。
右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。
論旨は、採用することができない。
同第四点及び第五点の一について
所論は、要するに、本件救済命令における「上告人会社は、支部所属組合員に対して時間外勤務(休日勤務を含む)を命ずるにあたつて同支部組合員であることを理由として他の労働組合員と差別して取り扱つてはならない。」との主文は、抽象的にすぎて不明確であり、また、これが支部所属組合員に対しては無条件の自由意思による残業を命ずべきものとしたものとすると、E労組所属の組合員との間に逆差別をもたらすものであるにもかかわらず、原判決がかかる救済命令を適法としたのは、法令の解釈、適用を誤り、理由不備、理由齟齬の違法を犯したものである、というのである。
思うに、労働委員会は、当該事件における使用者の行為が労組法七条の禁止する不当労働行為に該当するものと認めた場合には、これによつて生じた侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の回復、確保を図るために必要かつ適切と考えられる是正措置を決定し、これを命ずる権限を有するものであつて、かかる救済命令の内容(主文)の決定については、労働委員会に広い裁量権が認められているものといわなければならない。
したがつて、裁判所は、労働委員会の救済命令の内容の適法性が争われている場合には、労働委員会の右裁量権を尊重し、その行使が右の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、又は著しく不合理であつて濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではないのである
(最高裁昭和四五年(行ツ)第六〇、第六一号同五二年二月二三日大法廷判決・民集三一巻一号九三頁参照)。
これを本件についてみるに、本件において労組法七条三号の不当労働行為を構成するとみるべきものは、前記のとおり、次のような経緯における上告人会社の一連の行為である。
すなわち、上告人会社は、旧Dとの合併後旧Dの工場にもE型交替制及び計画残業方式を導入したものであるが、その導入にあたり併存組合の一つであるE労組とのみ協議し、支部に対してはなんらの提案も行わずに一方的にその組合員を昼間勤務にのみ配置し、かつ、一切の残業に組み入れないという措置をとつた。
これは、労働条件の決定等に関する交渉相手として支部の存在を無視し、その組合員を差別的に取り扱う意図の窺われるもので、支部の団結権に対する侵害行為である。
上告人会社は、その後支部からの要求により右の残業に関する会社の措置が団体交渉事項となつたのちも、右残業問題について解決するための誠実な団体交渉を行わずに最初の措置を維持継続してこれを既成事実と化し、結局、会社が残業の条件とする交替制勤務及び計画残業についての協定が支部との間に成立しない限りその組合員に残業を命じないとの態度を固執して右既成事実を維持継続した。
これは、団体交渉における膠着状態を継続することによつて支部所属の組合員を経済的に圧迫し、ひいて支部内部の動揺あるいは支部の弱体化を生ぜしめんとの意図が主たる動機・原因となつているものと推断させる行為である。
右のとおり、本件不当労働行為は、上告人会社が旧Dの製造部門にE型交替制と計画残業方式とを導入した機会に始まるものであり、それ以前においては、旧Dの製造部門においては右と異なる勤務体制及びD方式による残業が実施されていたのである。
したがつて、上告人会社が右のような旧Dにおける労働条件を変更するについて支部の存在を無視し、これに対しなんらの提案も行わないで、一方的にその組合員を一切残業に組み入れないとの措置をとり、このようにして形成した事実を前提として支部との団体交渉に臨むという会社の一連の行為が不当労働行為とされた以上、これに対する原状回復措置として、支部との関係においては、その組合員を一切残業に組み入れないとの措置をとる以前の状態に戻すことを命ずる趣旨で、残業について支部所属組合員であるがゆえの差別をしてはならない旨を命じたとしても、これは労働委員会に認められた裁量権の限界を超えたものということはできない。
そして、本件救済命令の主文は、正に右の趣旨を命じているにすぎないものと解せられるから、これをもつて抽象的、不明確であるとしたり、逆差別を命ずるものであるとするのはあたらない。
ところで、本件救済命令に従うと、支部が前記交替制勤務又は計画残業について同意しない限り、これとの間に協定が締結されず、かくして会社は、大多数の従業員が交替制及び計画残業に服しているにもかかわらず支部所属の組合員については昼間勤務にのみ配置した状態でD方式による残業を命じなければならないこととなつて不合理であるとする見解があるかもしれない。しかし、そのような非難はあたらないと考えられる。
すなわち、本件救済命令は、先にも述べたとおり、残業について支部所属組合員であるがゆえの差別をしてはならない旨を命じたものであつて、その趣旨によれば、要するに、団体交渉の過程において残業について右の差別を行わない限り、その組合員を、先にE労組との間で協議を経て実施している交替制及び計画残業に組み込むことについて更に支部と団体交渉を重ねることとするか、これをも振出しに戻して新たな勤務体制及び残業方式を模索するかは、上告人会社が自由に決しうることである。
仮に、支部所属組合員を右交替制及び計画残業に組み込む方向で更に支部と団体交渉することとした場合に、製造部門において残業を交替制勤務と切り離して取り扱うこと及び計画残業に対する支部の不協力が現実に上告人会社の業務遂行に支障を生ぜしめるものであり、支部との団体交渉において、誠意を尽くして説得しても支部が右勤務体制に服することをがえんじようとしないのであれば、かかる現実的障害の発生に対する会社の対抗措置として、以後支部所属組合員を残業から排除すべきことを提案し、これに対する支部の意思決定を求め、そのうえでこれに応じた措置をとることは、なんら非難さるべきことではない。
要するに、上告人会社が、本件残業問題に関し、支部及びその所属組合員を差別した以前の労働条件に事実上回復したうえで、支部との団体交渉を誠実に尽くすならば、会社がその要求である勤務体制及び計画残業方式を強く主張することにはそれなりの合理性が認められることは先にみたとおりである。
そして、支部がその団体交渉において結局自己の要求を通すことができないこととなつたとしても、それは団結
力、交渉力の問題であるのにすぎない。
原判決の説くところも結局以上と同旨をいうものと解せられ、原判決に所論の違法があるとは認められない。
論旨は、採用することができない。
同第五点の二について
間接部門の支部所属組合員に対し残業を命じなかつた上告人会社の行為が労組法七条三号の不当労働行為にあたるものであることは、先に上告理由第二点及び第三点に関して言及したとおりである。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第五点の三について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件救済命令存続の必要性が失われたとはいえないとした原審の判断は、正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、
不当労働行為の成否に関する上告理由第二点、第三点及び第五点の二につき
裁判官木戸口久治の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
kuma
以下、木戸口裁判官、の意見が続きます。
違う考え方もある、と参考になりました。
判例の理由内容と混乱を避けるため、
記載にとどめ、マーカー等はしていません。
裁判官木戸口久治の反対意見は、次のとおりである。
私は、本件救済申立事件における不当労働行為の成否については多数意見と見解を異にし、本件において上告人会社が支部所属組合員に残業を命じなかつたことについて不当労働行為は成立しないと考える。
一 私も、次の点については多数意見と完全に見解を同じくするものである。
1 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合に、一方の組合は、使用者との間に一定の労働条件のもとで残業することについて協約を締結したが、他方の組合は、より有利な労働条件を主張し、右と同一の労働条件のもとで残業をすることについて反対の態度をとつたため、残業に関して協約締結に至らず、その結果、右後者の組合員が使用者から残業を命ぜられず、前者の組合員との間に残業に関し取扱に差異を生ずることになつたとしても、それは、ひつきよう、使用者と労働組合との間の自由な取引の場において各組合が異なる方針ないし状況判断に基づいて選択
した結果が異なるにすぎないものというべきであつて、残業について両組合員間に右のような取扱上の差異を生ずるような措置をとつた会社の行為につき不当労働行為の問題は生じないものといわなければならない。
2 上告人会社が支部との団体交渉において、支部に対し、製造部門においては上告人会社がE労組との労働協約に基づき実施しているのと同一の労働条件のもとに支部所属組合員が計画残業に服することについて合意することを強く主張し、支部が右会社の提案に同意しない限りその組合員に対する残業組入れを全面的に拒否する旨の態度を示したことについては、合理的な理由がある。
二 ところで、多数意見が本件における残業に関する上告人会社の措置につき不当労働行為の成立を認めたのは、団体交渉における支部に対する上告人会社の要求が合理的かつ正当性を承認しうる面を備えているとしても、その真の決定的動機が少数派組合である支部に対する団結権否認ないしその弱体化にあり、本件の残業問題に関する団体交渉が右の意図に基づく既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる、と評価したことによるものである。
しかし、私は、多数意見の右の評価については到底賛成することができない。
その理由は、以下のとおりである。
三 まず、多数意見は、上告人会社が合併後旧Dの製造部門にE型交替制と計画残業の勤務体制を導入するについて、当初E労組とのみ協議してその導入を決定し、支部とはなんらの協議も行うことなく、一方的に支部所属組合員を早番勤務(昼間勤務)にのみ配置し、かつ、右導入以後同組合員につき一切の残業への組入れをしなかつたことについて、正当な理由があつたとは認められないとし、上告人会社の右のような態度は支部の存在を無視して企業の運営を図ろうとする意図のあらわれとみられてもやむをえないところである、としている。
しかし、このような多数意見の見方は、右勤務体制に対する支部の反対の意思表明の事実を過小に評価しているものであつて、同調することができない。
1 合併前旧Dにおける唯一の労働組合であつた支部においては、会社の合併及び合併後のE労組との組織統一等をめぐつて態度決定を迫られ、支部執行部及びこれを支持する少数の組合員は合併により既得の労働条件が低下するおそれがあるなどとして合併に対し消極的であつたのに対し、むしろ圧倒的多数の組合員は合併に積極的であり、結局、約九八パーセントの組合員は支部の属していたC2から組合として脱退する決議を行い、合併後はE労組に統合することを予定して、組合の名称をD自工組合とした。そして、D自工組合は、旧Dとの間において合併後は上告
人会社の就業規則によることについて基本協定を締結した。
一方、右の過程において、C2に所属する支部は依然存続するものであるとして、一五二名の組合員名を旧Dに通告した。
これが現在の支部である。
支部がE型交替制及び計画残業について容易に妥協を示さないのは、会社の合併をめぐり支部内部に生じた組合員間の意見の対立を経て、少数派組合として残存することとなつたという基本的立場と関係しているものであることが右によつて明らかであると考えられる。
2 すなわち、支部は、上告人会社が合併後旧Dの工場にE型交替制及び計画残業を導入する前から深夜勤務反対等の旨を情宣活動等において表明し、また、右導入後支部所属組合員が計画残業に組み入れられなかつたことについて、当初これを差別的取扱として抗議したり、是正を要求したりすることもなかつた。
そればかりか、支部は、昭和四二年三月から六月ころまでの間、春闘やメーデー参加等に際して、「会社の残業政策を粉砕しよう」、「労働条件を合併前に戻せ」、「深夜勤務の強化、夜勤の早出、隔週夜勤反対」、「残業、公出……の強制反対」、「強制残業、深夜勤務はすぐやめよ」、「残業は自由意思でやらせろ」等の記載のあるビラを配布していたのであつて、このような事実からすると、支部は、上告人会社の採用している右勤務体制を知つたうえで、計画残業を強制残業であるとして、あえてこれに反対していたものであることが明らかであるといわなければならない。
3 このように、支部は、合併後旧Dの製造部門にE型交替制及び計画残業が導入される前から情宣活動等を通じて右勤務体制に反対の意思を表明してきたものであり、その態度は明確かつ強固なものであつた。
このような場合に、上告人会社があえて支部に対し右勤務体制の導入・実施について団体交渉の申入れをしたとして
も、右交渉において支部の同意を得ることは到底不可能であつたことは客観的にも明らかであつたといわなければならず、上告人会社がE労組の同意を得たのみでE型交替制及び計画残業を旧Dの製造部門に導入したことはやむをえなかつたものであり、これをもつて支部を無視する処置であつたとして上告人会社を非難することは当たらない。
4 そして、右のようなE型交替制及び計画残業の導入に伴う措置として、上告人会社が製造部門における支部所属の組合員を早番勤務にのみ配置し、かつ、これに対し残業を命じない措置をとつたのは、支部がE型交替制のもとでの遅番勤務(夜間勤務)に反対し、計画残業は強制残業であるとしてこれに反対していたため、上告人会社が、このような支部の反対がある以上その所属組合員を右交替制のもとでの遅番勤務に組み入れることができないと考え、また、計画残業に非協力の態度を表明している支部所属の組合員をこれに組み入れるならば右計画業務の遂行に支障を生ずるおそれがあることを懸念し、他方早番勤務にしか従事しない者を残業に従事させることは、E労組所属の組合員が右交替制勤務体制に服し、遅番勤務に引き続く残業に従事していることと均衡を失することになるとの考慮によるものと認められるのであつて、このような上告人会社の判断になんら不当、不合理な点はなく、むしろ当時の支部の態度からみれば当然のことというべきである。
結局、上告人会社がE型交替制及び計画残業の勤務体制実施当初から支部所属組合員を残業に組み入れなかつたのは、支部がその自主的な判断に基づき自らその組合の方針として上告人会社の勤務体制に反対することを選択したことによる結果に外ならないというべきであるから、これについて上告人会社に責めらるべきところはなく、上告人会社のとつた措置につき不当労働行為が成立する余地はないといわなければならない。
四 次に、多数意見は、本件残業問題について支部との団体交渉が行われた昭和四二年六月以降における上告人会社の交渉態度が不誠実なものであつたと評価している。
しかし、上告人会社の交渉態度をもつて不誠実であつたとする多数意見には、同調することができない。
1 上告人会社と支部は昭和四二年三月二二日を第一回として正式な団体交渉を持つに至つたが、支部が残業問題に関し上告人会社に団体交渉を申し入れたのは同年六月以降である。
そして同年六月三日から一一月二八日までの数回の団体交渉において本件残業問題について交渉が行われたが、上告人会社は、支部が計画残業を強制残業であるとしてこれに反対している限り信用も信頼関係も生まれないと主張し、支部が右のような態度を改めることが残業問題の交渉についての前提条件であることを示し、E労組所属の組合員と同一の労働条件のもとでの交替制及び計画残業の勤務体制に支部所属組合員も服することを求めたのに対し、支部は、残業に絶対反対とはいつていない、三六協定に基づく残業には以前から協力してきた、ただ上告人会社の主張する計画残業は強制残業であるからこれに反対だといつているのだと主張して応酬し、同年一二月一五日には、逆に支部側から、夜間勤務に応ずる条件として、週五日制とすること、昼間よりベルトコンベアのスピードを落とすこと、夜勤手当を増額することなどを要求し、同月二七日都労委に本件残業問題をめぐる紛争についての斡旋を申請したのである。
2 以上のような交渉の経緯からすると、そこでいう計画残業というのは、E型交替制と組み合わされた残業を指すものであることはいうまでもないところであるから、上告人会社と支部との間においては、支部がE型交替制及びこれと組み合わされた計画残業を受け入れるかどうかがいわば最終的な攻防の目標として、本件残業問題に関する団体交渉が行われていたことが明らかであつて、上告人会社において支部に対しE型交替制及び計画残業を受け入れることが残業を命ずる条件であるという主張をしたことが明示的でなかつたとしても、それが上告人会社の態度であることは支部も十分了知していたところというべきである。
そして、支部の側において右E型交替制及び計画残業を受け入れる意思がみられない以上(支部が提案した前記のような夜間勤務に応ずる条件が上告人会社によつて拒否されることは常識的に考えて明らかである。)、団体交渉が前記のような応酬で推移したのはやむをえないところであつて、この間の上告人会社の交渉態度が不誠実であつたとするのは当たらない。
3 支部の前記条件の提示を受け、都労委の斡旋員の勧告により行われた昭和四三年一月二六日の団体交渉において、上告人会社は、支部に対し、E労組との労働協約に基づき実施しているのと同一の労働条件のもとに支部所属組合員が計画残業に服することについて合意することを強く主張し、支部が右会社の提案に同意しない限りその組合員に対する残業組入れを全面的に拒否する旨の態度を示したのに対しても、支部は、あくまで右会社の提案する条件のもとでの夜間勤務には応じられないとし、その立場は会社側の説得の余地に乏しく、結局右団体交渉も決裂に終わつた。
さらに、本件初審命令が発せられた後の昭和四六年六月一八日から翌四七年四月一八日までの間にも、八回にわたり本件残業問題に関する団体交渉が行われ、上告人会社は、支部に対し、重ねてE労組所属の組合員と同様の労働条件のもとに支部所属組合員もE型交替制及び計画残業に服するよう申し入れた。
しかし、支部は、E型交替制に伴う遅番勤務に服することを認めるか否かは上告人会社の生産計画、設備計画等一切の関連要素を検討し、これらを煮つめたうえで結論を出すべきであるなどとして、遅番勤務反対の従来の立場を主張したため、結局合意をみるに至らなかつたものである。
4 これら数次にわたる団体交渉において上告人会社が堅持してきた立場、すなわち、E型交替制と計画残業の勤務体制を支部に対しても要求し、右勤務体制に服することについて合意しない限り支部所属組合員に対する残業組入れを全面的に拒否するという態度に終始した上告人会社の立場についていえば、E型交替制と計画残業の勤務体制は、既に合併前から上告人会社においてE労組との労働協約に基づきこれが一体のものとして実施されてきたものであり、合併後の旧Dの事業場においても、旧D従業員全体の約九八パーセントの労働者をもつて組織するD自工組合及びこれを包摂することになつたE労組との合意に基づき右勤務体制及びその体制のもとでの計画残業が導入され、実施されてきたものである以上、本件におけるように旧D従業員全体の二パーセントにも満たない労働者で組織する支部と前記圧倒的多数の労働者で組織するE労組とが併存している状況のもとにおいては、使用者としては、勤務体制のように一つの事業場において全従業員に共通して適用することが労務管理上必要な事項については、多数労働者の意思を尊重する意味でも、両組合の交渉力の関係からいつても、前記のような組織力を持つ多数派組合であるE労組との交渉又はその交渉結果に重点を置いて対処せざるをえないのが実情であつて、上告人会社が同一事業場に二様の勤務体制をとることは不可能であるとして、支部との団体交渉において、支部に対し、先に圧倒的多数の従業員を擁するE労組との間で合意をみたのと同一の勤務体制及びこれに組み合わせて一体として実施している計画残業に支部が服することを強く主張し、これに固執したとしても、これをもつてなんら不当な交渉態度であると非難することはできないものといわなければならない。
5 一方、支部は、前記のように、旧Dの事業場に右勤務体制が導入される以前から情宣活動等を通じて、夜間勤務には反対である意思を表明し、かつ、計画残業は強制残業であるとしてこれに反対していたのであり、また、長期にわたる団体交渉の過程を通じても、E労組と同一の労働条件のもとでは右勤務体制に服することはできないとして、上告人会社の提案する残業の条件を拒否し続けてきたものであつて、このような支部の態度からすれば、前記情宣活動以来支部において表明してきたものが単なる建て前やスローガンとしての反対にすぎなかつたものとは到底いえないところである。
そして、支部は、その主観的意図はともかく、客観的にみれば、旧Dの従業員の単位でみてもわずか全体の二パーセントにも満たない労働者しか擁していない少数派組合であるにもかかわらず、約九八パーセントの労働者を擁するD自工組合及びこれを包摂したE労組が協約を結んだ勤務体制に反対し、これよりもより有利な労働条件でなければ右勤務体制及びそのもとでの計画残業に服さないと主張し、かつ、その立場で上告人会社の提案する残業の条件を拒否したものであつて、このような客観的な情勢をわきまえない支部の立場に譲歩しなかつた上告人会社の団体交渉の態度に不当な点があるものとは考えられない。
6 以上のような点に鑑みると、上告人会社が旧Dの製造部門にE型交替制と計画残業とを導入・実施することになつた昭和四二年二月一日以降、支部所属の組合員に残業を命じない措置をとり、これを継続してきたのは、結局は支部がE労組が受け入れたのと同一の労働条件のもとでの残業に服することを拒否し続けたことにより上告人会社と支部との間に残業問題に関する労働協約が締結されるに至らなかつたことが唯一の原因であるというべきであつて、その結果として、支部所属の組合員が残業に就きえなかつたとしても、それは支部が自主的な判断に基づき、自ら
選択した結果に外ならず、かかる団体交渉の経緯をもつて上告人会社が専ら差別状態をもたらそうとして故意に協約の締結を阻害した結果であるとか、あるいは上告人会社が支部に対し前記のような残業の条件を提示してこれを堅持してきたことの主たる動機・原因が、支部所属組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより、組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものであつた、などということは到底いいえないところである。
五 なお、多数意見は、合併の前後において上告人会社の行為に不当労働行為とされるものがあつたことを上告人会社の不当労働行為意思を認める一つの事情としているようであるが、上告人会社が支部に対する一般的な反感を有していたことを窺わせるものがあつたとしても、本件の問題における上告人会社の態度が不当労働行為意思あるいは支部に対する反感に根ざすものとみることはできないものといわなければならない。
六 以上の次第であるから、私は、製造部門における支部所属組合員の残業組み入れ拒否は、なんら支部に対する支配介入として不当労働行為を構成するものではないと考える。
七 次に、間接部門についてみると、確かに同部門においては遅番勤務がなく、交替制と組み合わされた計画残業を実施しているわけではないから、同部門における支部所属組合員に残業をさせるかどうかは前記交替制勤務や計画残業に対する支部としての反対の態度とは切り離して考えなければならない問題である。
したがつて、上告人会社が間接部門に勤務する支部所属組合員に対しても昭和四二年二月以降一切残業を命じないとする措置をとつたことについては、客観的にみれば正当な理由があるとすることはできない。
しかし、そうであるからといつて、多数意見のように直ちにこれが支部に対する支配介入意思に基づくものであると推断するのは正当とはいえないと考える。
その理由は次のとおりである。
1 間接部門における残業は、各職場の職制が業務の必要に応じて個々に残業を命ずるのであるが、旧Dの事業場においては、会社の合併をめぐり旧Dの従業員の大多数がむしろ積極的に上告人会社との合併を望み、これに消極的な執行部と対立し、C2から脱退する決議を行い、D自工組合を結成した経緯から、支部に残留した組合員とD自工組合結成に動いた大多数の従業員との間に感情的な対立を生じ、双方の組合員が職場内で反目し合う状況が生じた。このような状況のもとでは、上告人会社が、E型交替制及び計画残業に反対する情宣活動等を強力に展開していた支部所属の組合員に対し残業を命じても十分な残業の成果をあげることはできないと判断したとしても、無理からぬ点があつたというべきである。
また、支部は、製造部門、間接部門を問わず、その所属組合員が昭和四二年六月まで残業を命じられなかつたことに抗議したり、是正を要求したりすることはなかつたのであって、これは、当時の職場の状況のもとにおいては、支部所属の組合員を残業から排除する措置をとつた上告人会社ないし各職場の職制の判断にもそれなりの合理性があつたことを裏付ける事情になるものと考えられる。
2 のみならず、上告人会社は、昭和四六年六月一八日から翌四七年四月一八日までの八回にわたる支部との団体交渉において、製造部門の問題と間接部門の問題とを明確に区別する態度に改め、支部に対し、間接部門については以後残業を命ずることとするからこれに服するよう提案したのにかかわらず、支部は、同部門における支部所属の組合員はほとんど残業を必要としないような作業や質の低い作業に就かされているのでその改善が先決であり、その点が解決されない限り右提案は受け入れることができないと主張して残業に就くことを拒否したのであつて、かかる支部の姿勢にもかかわらず、上告人会社が個々の支部所属組合員に残業を命じたとすれば、新たな紛争の種になることはみやすいところであるから、結局、上告人会社がその後も支部所属組合員に対し残業を命じなかつたことは、支部がその自主的な判断により前記のような条件を出して上告人会社の申入れを拒否したことの結果によるものというべきである。
3 したがつて、間接部門についてみても、上告人会社の措置は、なんら不当労働行為を構成するものではないというべきである。
八 以上の次第であるから、私は、本件において不当労働行為は成立しないとした第一審判決を正当として支持すべきものであり、右と異なる判断に立つ原判決は不当であるから、これを破棄して、被上告人の控訴を棄却する判決をすべきものと考える。
キーワード
複数労働組合。残業命令。不当労働行為。
kuma