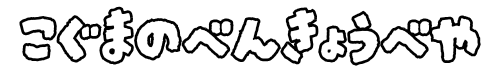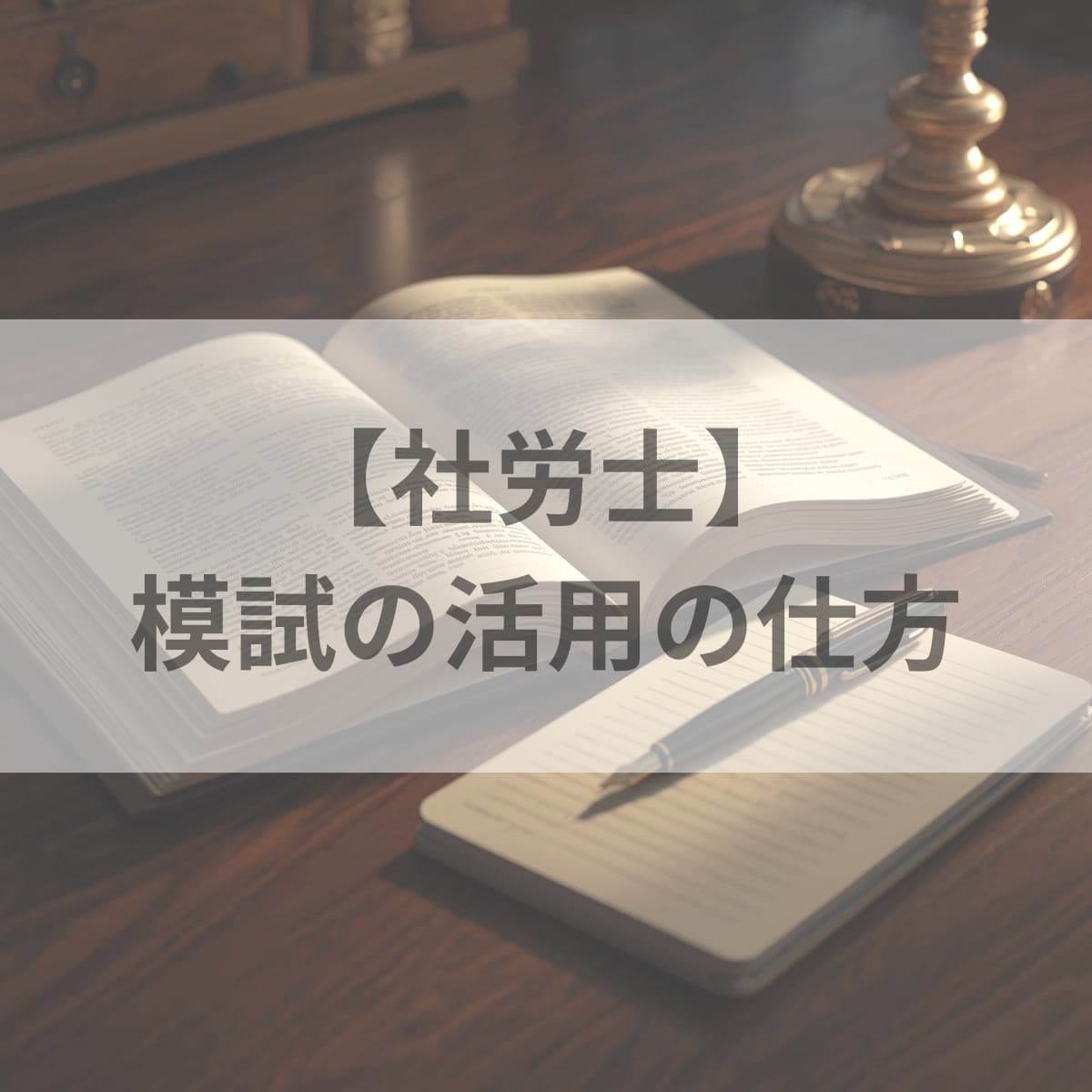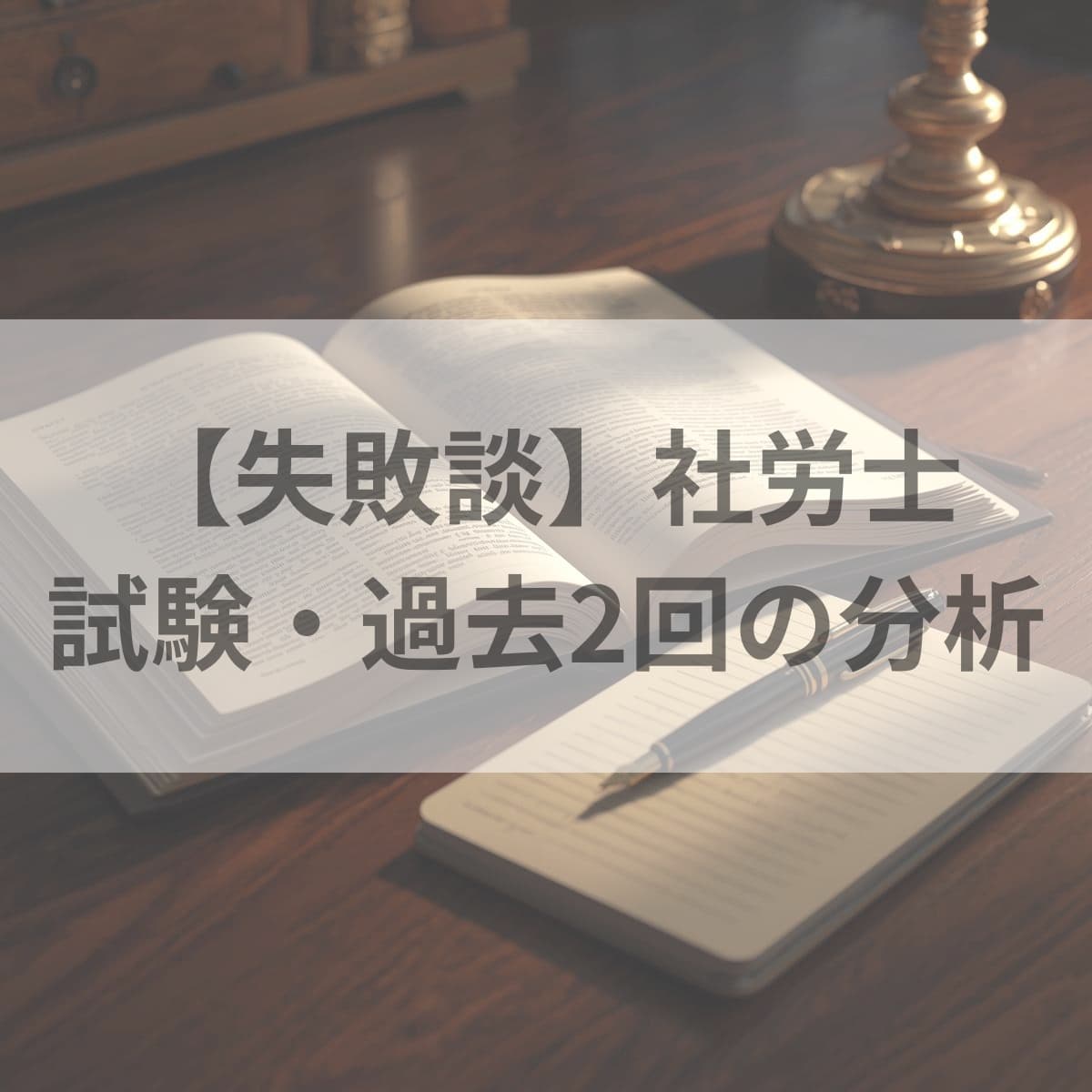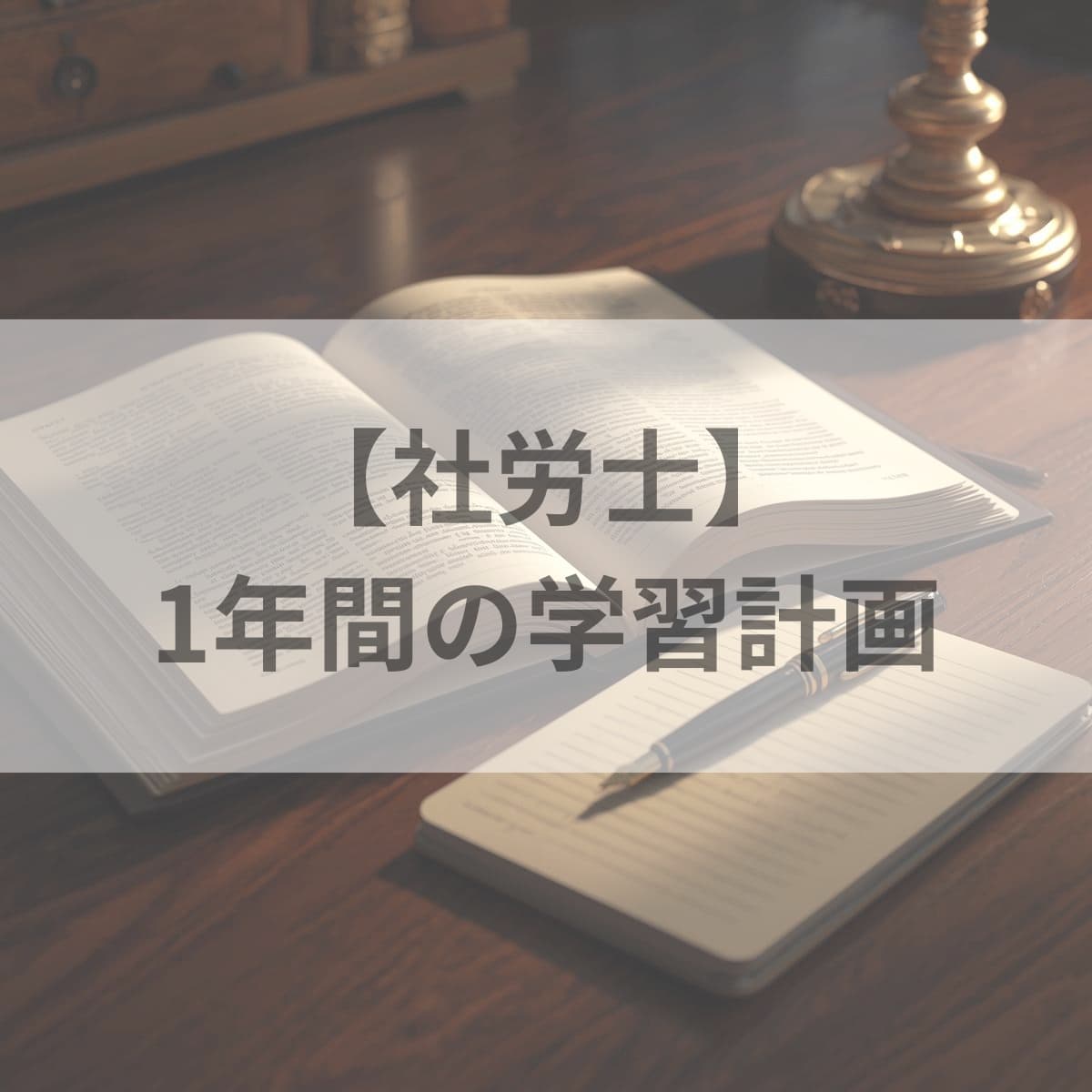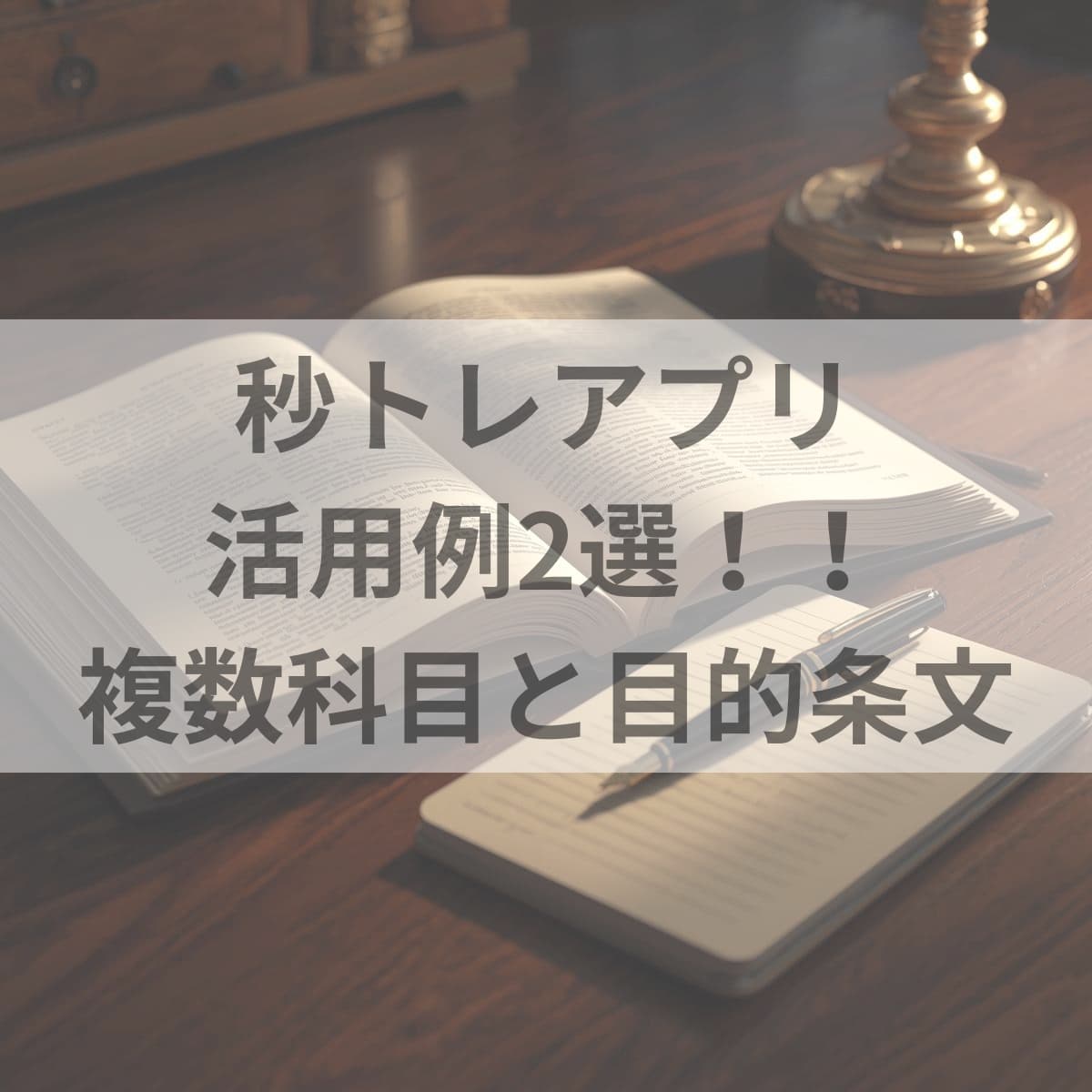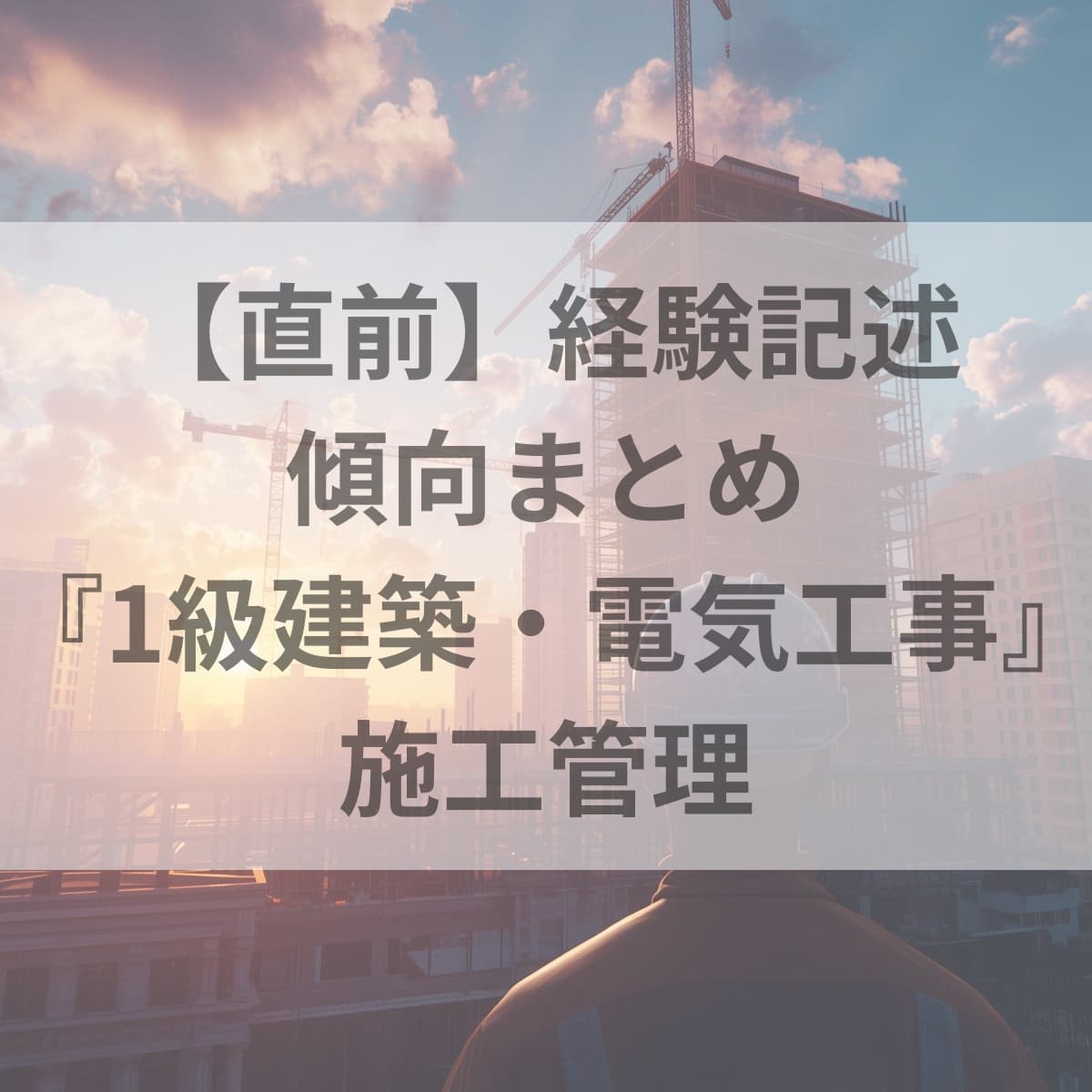こんにちは、kumaです!!
今回は模試の活用の仕方について書いていこうと思います。
『模試は何回受ければいいのか、、、』
『模試の復習はどうしたらいいのか、、、』
といった疑問があるかと思います。
素朴な疑問を受験生目線でお伝え出来たらと思います。
模試を受ける回数
まず、模試を受ける回数ですが、
2回~3回
が、標準かと思います。
理由としては、復習の時間が影響します。
選択式は40問ですが、
条文の穴埋めや判例の穴埋めといった、
一連の問題が多いので、復習に多くの時間がかかりません。
一方、択一式は70問の5肢あるので、
復習に350肢の確認をしないといけません。
1肢の確認(テキスト)つき、
5分かかるとして、1,750分(約29時間)
10分かかるとして、3,500分(約58時間)
必要です。(概算として)
kuma
選択式より択一式の方が、
復習の時間がかかるよ!!
模試のタイミングがそもそも直前期ですので、
残りの時間を考えると、現実的に2回~3回になろうかと思います。
kuma
模試は予備校受講生なら、
その予備校で実施しているものでOK。
独学者は市販のものや、模試の単科受講
を検討してみてください。
模試を受けた後
模試を受けたままにしてはもったいないです。
各予備校は最新のトレンドを踏まえて出題しているはずです。
間違えた問題、または、判断不明だった肢は、
テキストに戻って確認しましょう。
回答的には正解だったけど、論点が違ったものは特に要注意だと思っています。
見るべきキーワードを見落として、『たまたま』合っていただけで、
本質(論点)が見えていない、間違えているからです。
【応用】模試の受け方
応用的な模試の受け方を紹介します。
(※取り入れるかどうかは、各自の判断でお願いします。)
上で説明した通り、択一式の復習に、かなりの時間がかかることは説明しました。
では、選択式に限ってはどうでしょう。
復習の時間はそこまでかかりません。
思い切って、、、
『選択式だけ受ける』、
というのを前年試しました。
このうように考えた背景には、大手予備校が複数あることです。
受験生の一定の割合の人が受けている内容を、知らないことはリスクがあります。
その模試を受けていたら『拾える問題』に変わるということに直結します。
なるべく自分の知識を『多数派』に寄せることは大事かと思います。
『少数派』の内容は、出題されても『多数派』が解けない内容になります。
こちらのやり方は、ご自身の考え方、時間的な余裕等を勘案してください。
まとめ
模試の活用の仕方についてまとめました。
模試の回数については復習の時間を含めて計画しましょう。
受験後は必ず復習をしましょう。
応用的な受験の仕方については、参考にしてもらえたらと思います。
次回は年間計画について書いていこうと思います。
【関連記事】
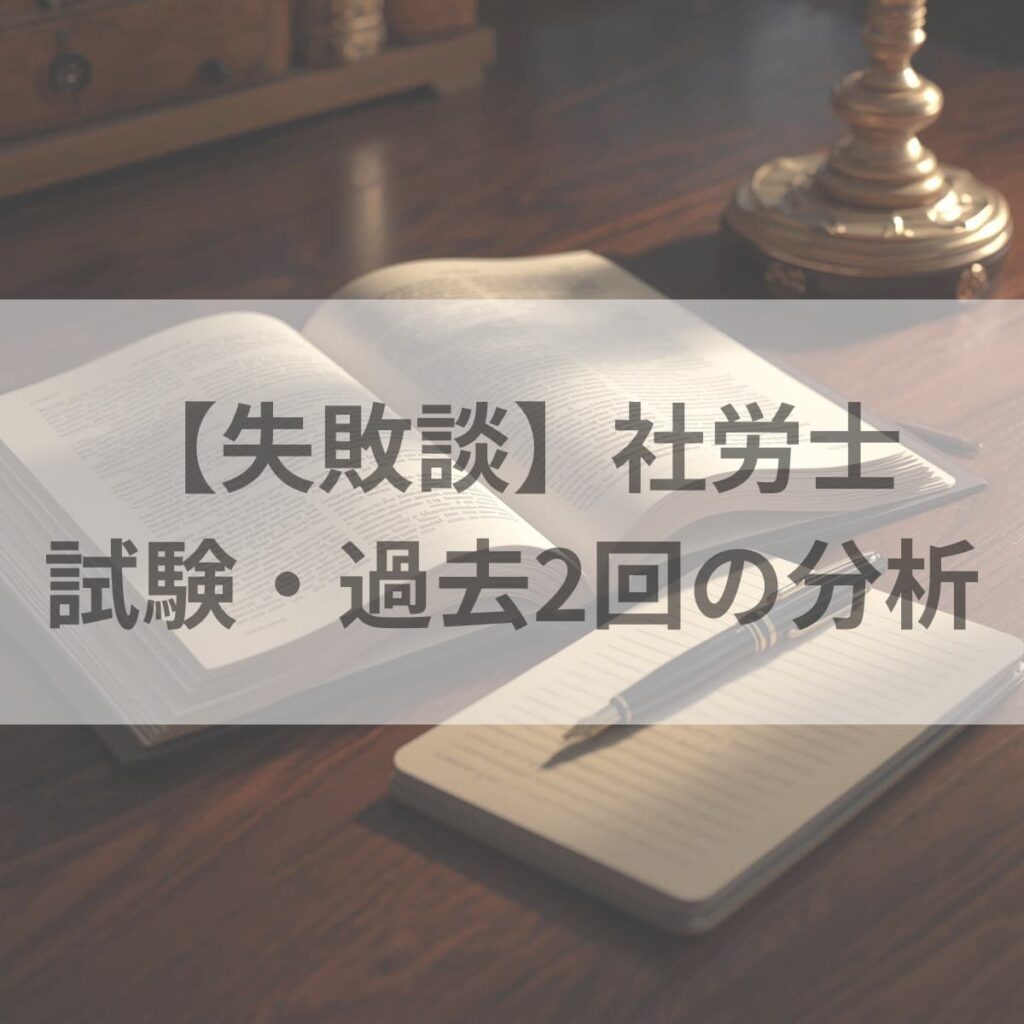
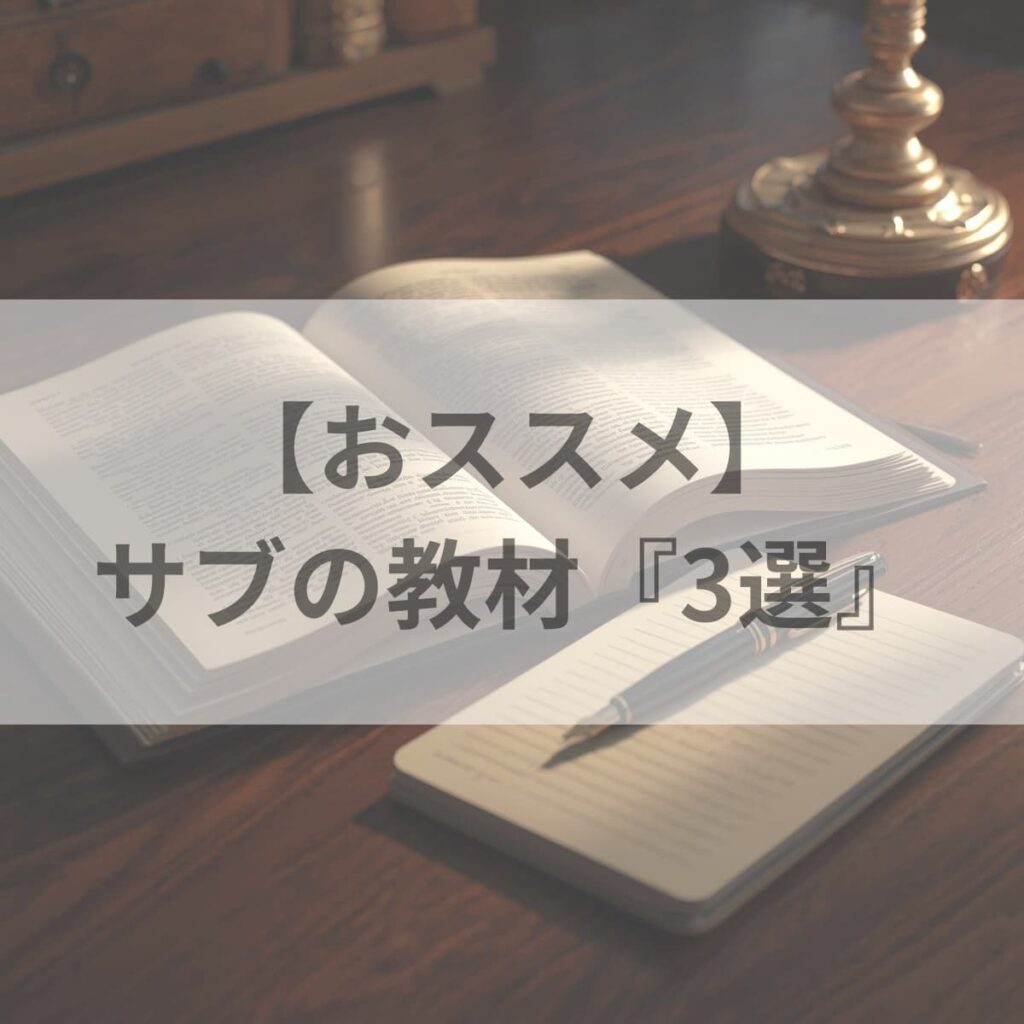
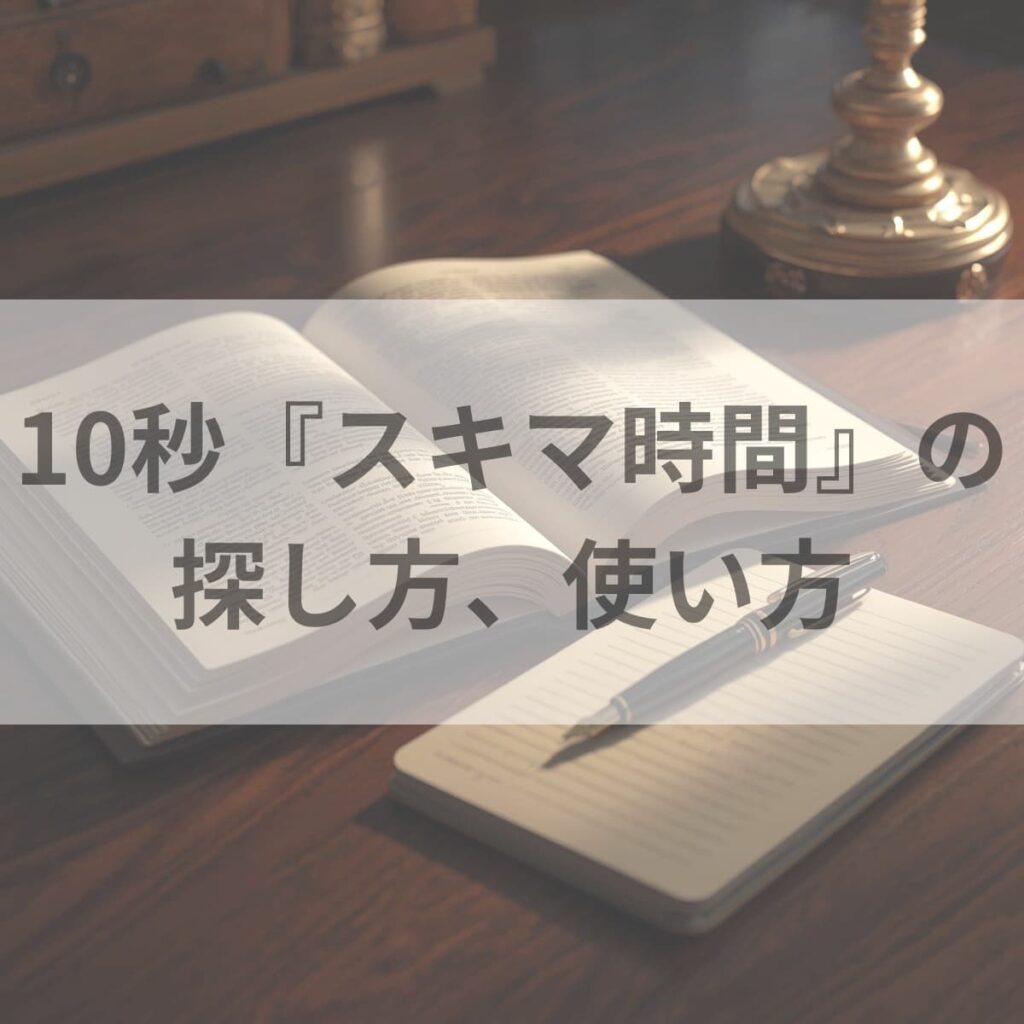
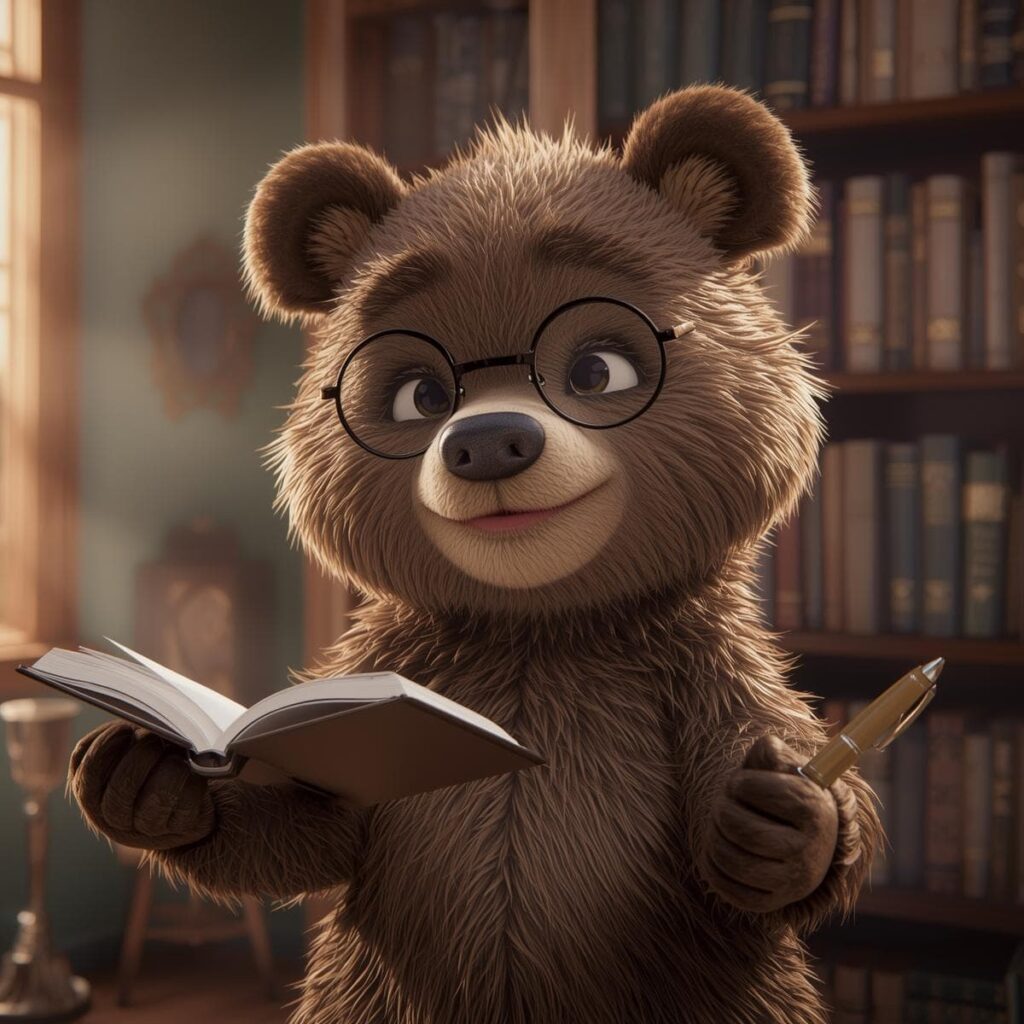
kuma