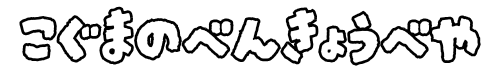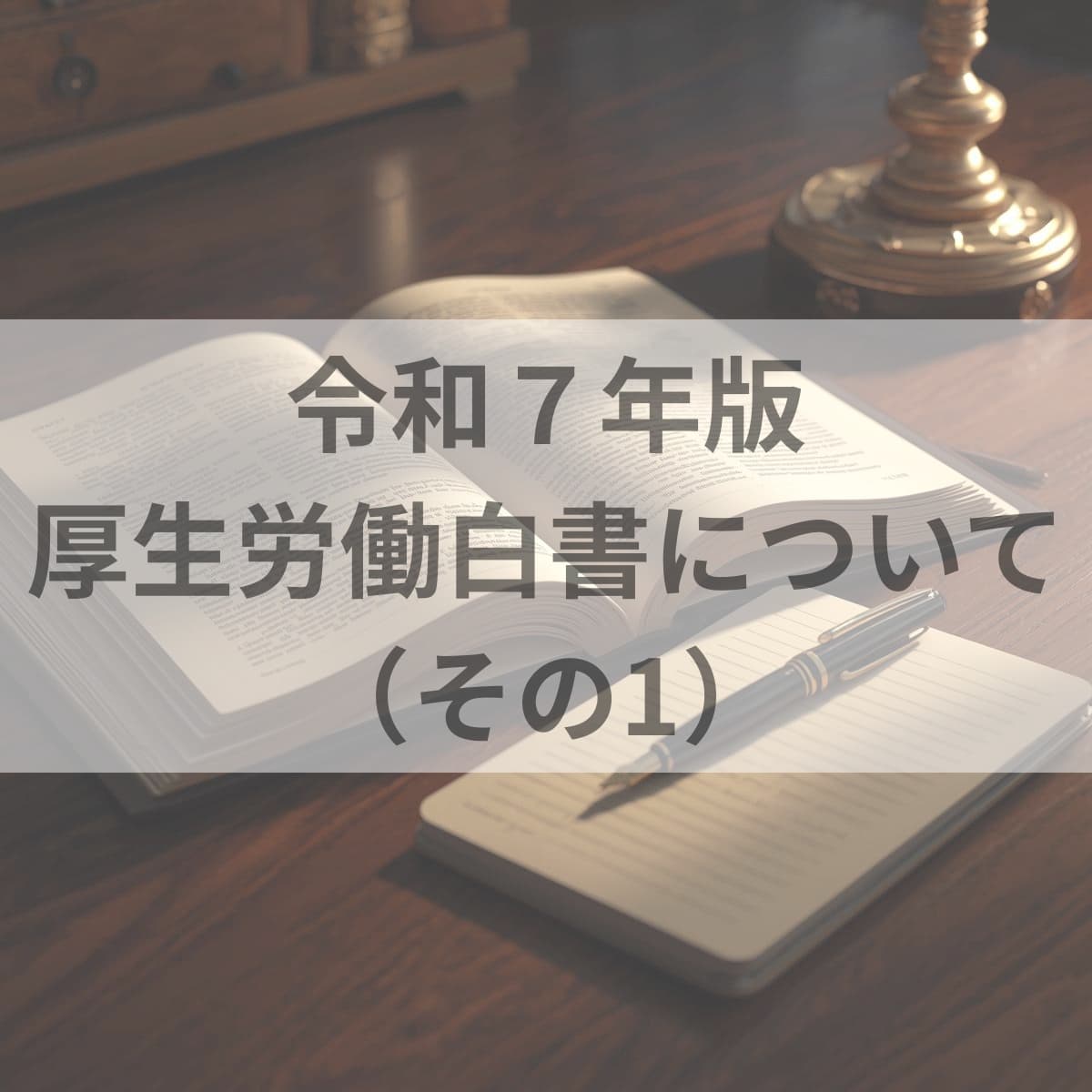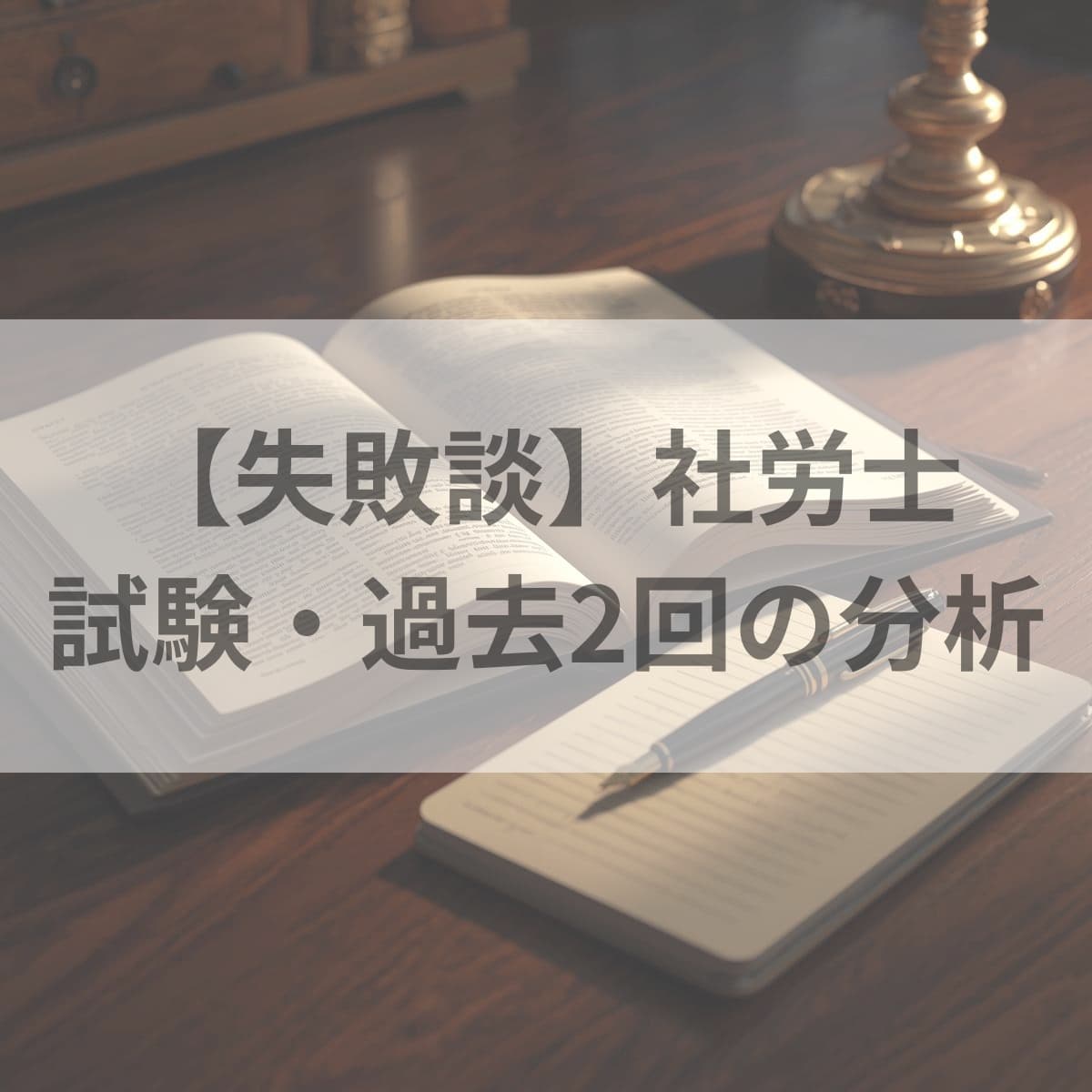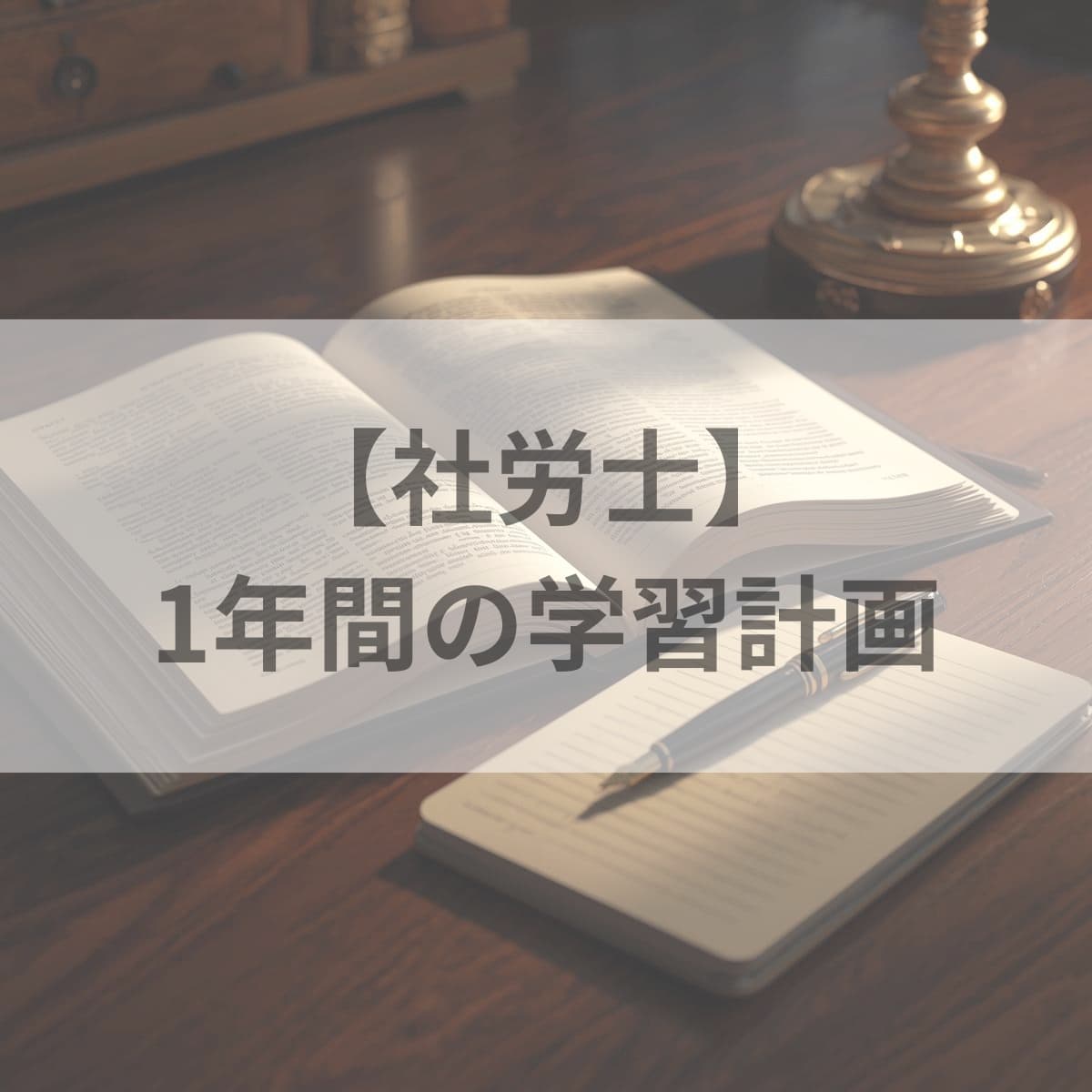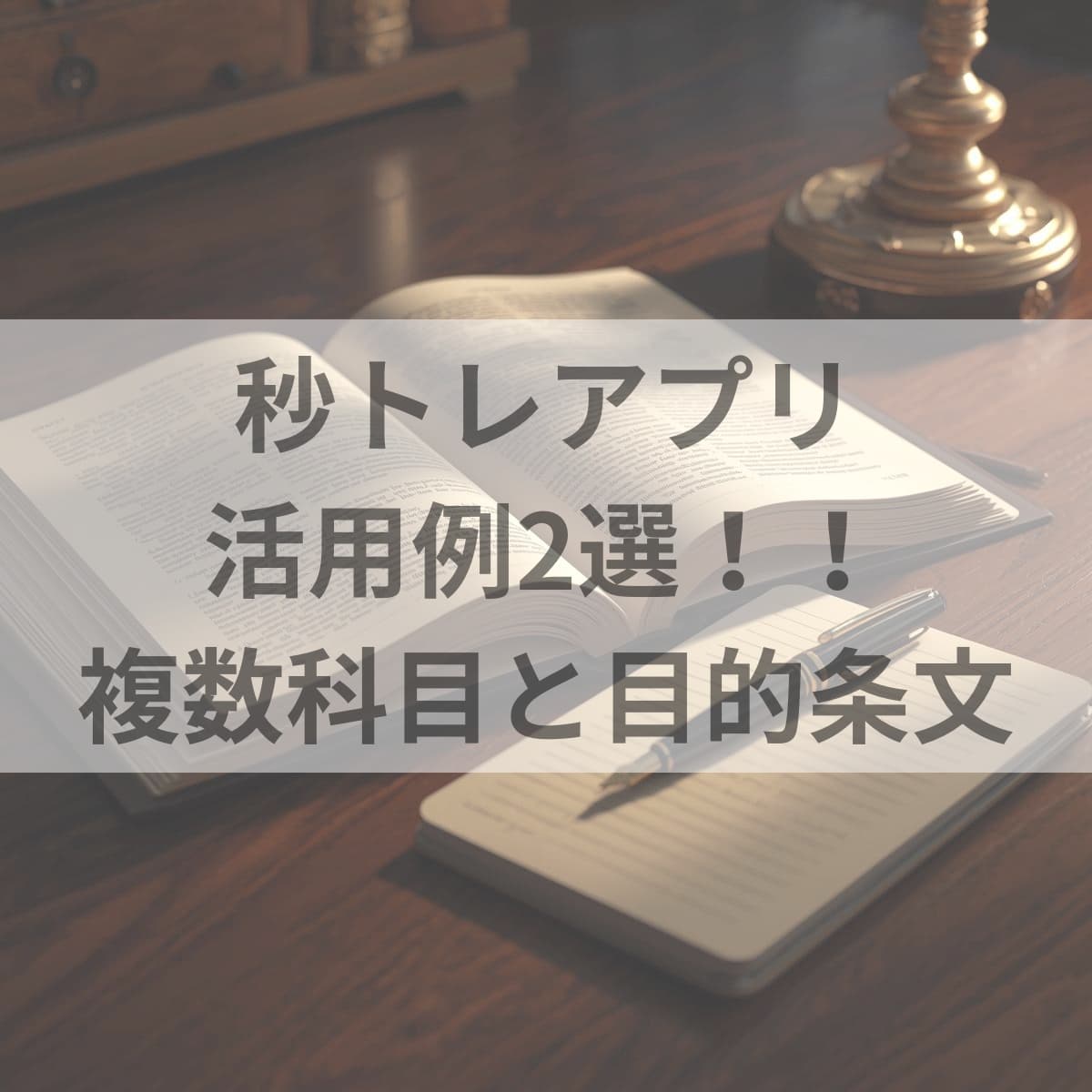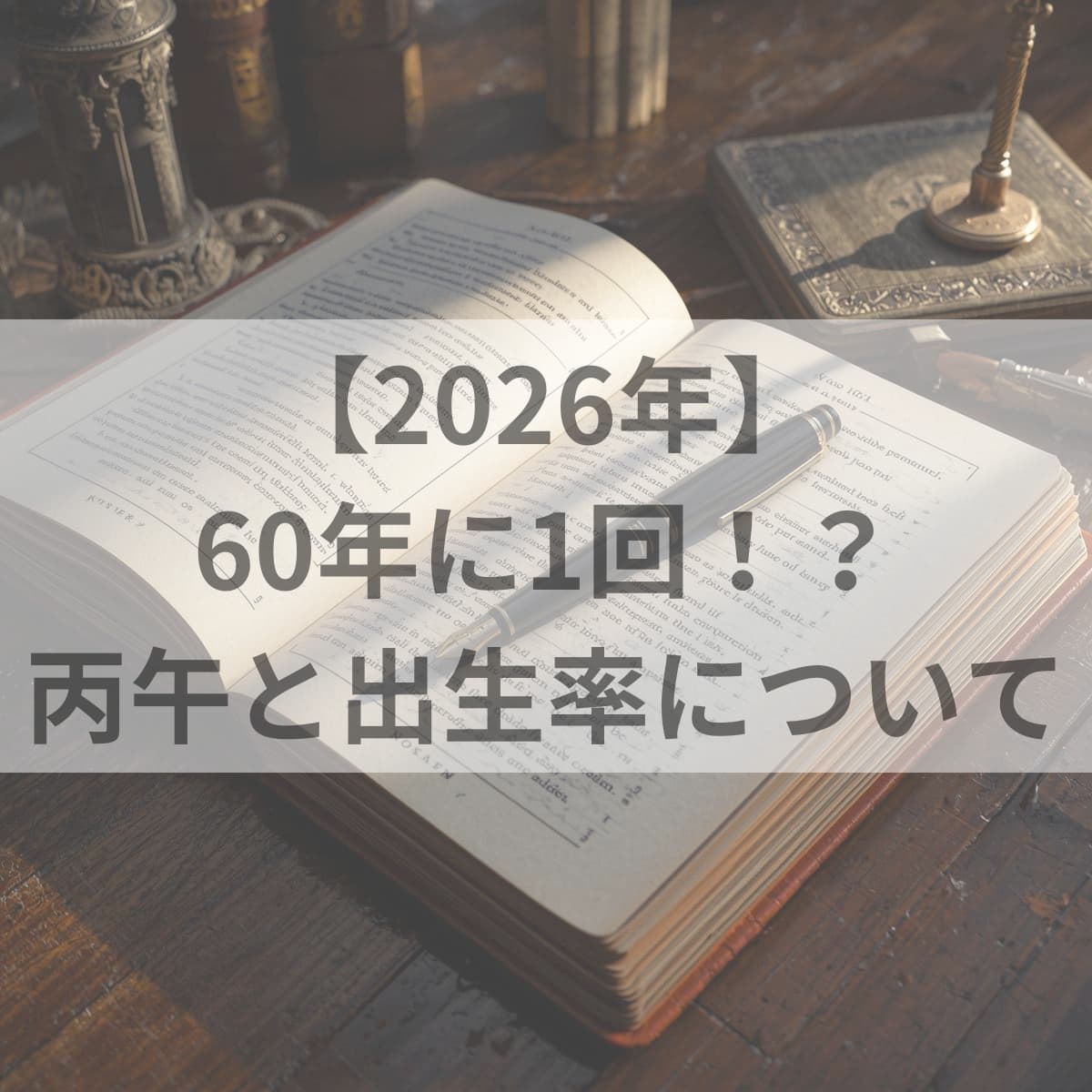こんにちは、kumaです!!
今回は、令和7年版厚生労働白書の概要について、書いていこうと思います。
(そのうち、今回は第1部について整理します。)
本記事は厚生労働省のHPより白書を抜粋参照したものになります。
また、概数でよいと思われる数値については『*』のマークを示します。
個人的に気なった箇所は吹き出しを用いて本文と区別できるようにします。
『社労士試験を見据えた記事』にしたいと思っております。
ですので、試験対策上不要と思われる箇所は『省略』を使用しております。
kuma
長文になります。
ご了承ください。
本文の構成は白書の章立てに即して作成しました。
ですので、本記事では不足と思われるところは、
下記の厚生労働省HPより該当の章を読み深めて頂けたらと思います。
本記事参照:厚生労働省 統計情報・白書 令和7年版厚生労働白書
第1部 次世代の主役となる若者の皆さんへ
―変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る―
はじめに・・・P.2~
次世代の主役となる若者の皆さんへ
~略~
今回の厚生労働白書では、第1章では社会保障や労働施策の役割について、
データも踏まえてまとめています。
現在、人口減少・超高齢社会が急速に進展する中で、
「全ての世代で社会保障を支え、社会保障は全ての世代を支える」という考え方に基づいて、
社会保障の見直しも進められています。
こういった点についても今回の白書では示しています。
第2章ではこれらを知ることの意義についてまとめています。
具体的なエピソードなどを盛り込んでいますので、
「たしかに、こういうことって自分の将来や自分の周りで起こりそうだよな」と思ってもらい、
少しでも社会保障や労働施策を身近なものに感じてもらえればと思います。
~略~
若者以外の皆さんへ
今回の厚生労働白書は、次世代を担う若者に、今後の人生において必要となるだろう社
会保障や労働施策について知ってもらいたい、自分事として考えてもらいたいという思い
から、なるべく若者に届くような平易な形で作成しました。
~略~
kuma
冒頭で「若者の皆さんへ」と
読者を若者と想定して作成されています。
「若者以外」は後段に記載されるに
とどまっています。
<読み方ガイド>
~略~
特に読んでほしいのは、第2章第2節です。
~略~
kuma
「読み方ガイド」という内容で、
特に読んでほしい、と
強調しています。
「第2章第2節 社会保障や労働施策を知ることの意義」
第1章 社会保障と労働施策の役割とこれから・・・P.5~
第1節 社会保障の役割
~略~
社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットだが、
①社会保険、
②社会福祉、
③公的扶助、
④保健医療・公衆衛生
からなり、人々の生活を生涯にわたって支えている。
~略~
~略~
それでは、社会保障の機能とはどのようなものだろうか。
主なものとして、
①生活の安定・向上、
②所得の再分配、
③経済の安定
の3つの機能があげられる。
~略~
第2節 労働施策の役割
~略~
主な労働施策の概要
①働く環境の整備
②公正な待遇の確保や柔軟な働き方がしやすい環境の整備
③多様な人材の活躍促進
④仕事と育児・介護や治療の両立支援
⑤働く人の能力向上への支援
⑥転職や再就職への支援、職業紹介等の充実
⑦労働保険
~略~
kuma
ここでは、概要だけ列挙しました。
第3節 人口減少・超高齢社会とこれからの社会保障・労働施策
~略~
現在、日本社会は、本格的な人口減少社会の到来という歴史的転換期にあるといえる。
日本の人口は、近年、減少局面を迎えており、2008(平成20)年をピークに減少に転じている。
高齢化率を見ると、1990(平成2)年には12.1%であったが、2020(令和2)年においては、
28.6%に達しており、急激な高齢化が進行している。
また、2050(令和32)年においては、総人口は10,469万人に減少すると推計されている。
~略~
今後の社会保障の在り方として重視されているのが「全世代型社会保障」である。
「全世代型社会保障」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障である。
この「全世代」は、若年期、壮中年期及び高齢期はもとより、
これから生まれる「将来世代」も含むものとして考える必要がある。
政府では、その在り方を議論する「全世代型社会保障構築会議」を開催し、
2022(令和4)年12月に報告書がまとめられた。
同報告書では、「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の方向性として、
①「少子化・人口減少」の流れを変える、
②これからも続く「超高齢社会」に備える、
③「地域の支え合い」を強める、
ということを示している。
~略~
出生数は、第2次ベビーブーム(1971(昭和46)~74(昭和49)年)以降、
減少傾向が続いている。
2024(令和6)年においては、68万6,061人(68万人*)であり、
前年の72万7,288人より4万1,227人減少している。
合計特殊出生率は、1989(平成元)年に1966(昭和41)年の「ひのえうま」を下回る
1.57となり、「1.57ショック」と言われ、
その後、低下傾向が続いていた。
2005(平成17)年の1.26以降は緩やかな上昇傾向にあったが、
近年は再び低下傾向にあり、
2024(令和6)年においては1.15であり、
前年の1.20より0.05ポイント低下した。
kuma
出生数、合計特殊出生率ともに
最低の値を記録。
男女ともに晩婚化が進むとともに、子どもを初めて持つ年齢についても上昇している。
平均初婚年齢を見てみると、
1990(平成2)年は男性28.4歳、女性25.9歳だったが、
2023(令和5)年は男性31.1歳、女性29.7歳と上昇している。
また、第1子出産時の母親の平均年齢を見てみると、
1990年は27.0歳だったが、
2023年には31.0歳となっており、
父親の平均年齢を見てみると、
1990 年は29.9歳だったが、
2023年には33.0歳と
なっている。
~略~
夫婦の間に生まれる子どもの数(完結出生児数)について、
国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査(夫婦調査)」を見てみると、
1940(昭和15)年には4.27だったが、
2021(令和3)年には1.90となっており、
家族の中で兄弟姉妹の数が減っていると考えられる。
~略~
50歳時の未婚率について見てみると、
1990(平成2)年には男性は5.57%、女性は4.33%だったが、
2020(令和2)年には男性は28.25%、女性は17.81%となっている。
今後、2040(令和22)年には男性は30.43%、女性は22.23%となると推計されている。
以前は、多くの人が結婚するような状況だったが、現在では結婚しない人も増えている
状況にある。
~略~
平均寿命については、
1990(平成2)年に男性75.92年、女性81.90年であったが、
2023(令和5)年には男性81.09年、女性87.14年になっており、
約30年間で5年以上伸びている。
~略~
女性の就業状況について見ていくと、
女性の就業率は30代後半を底として再び上昇していくいわゆるM字カーブの状況にあるが、
いわゆるM字カーブの底は、近年、浅くなっている。
一方、女性の正規雇用比率については、20代後半をピークに減少していく、
いわゆるL字カーブがみられる。
~略~
子どもの出産に当たって、仕事を辞める女性が多かったが、
2015(平成27)年から2019(令和元)年の第1子出産前後の女性の継続就業率は約7割となっており、
近年大きく上昇している。
また、雇用形態別にみると、正規職員は育児休業による継続就業が進んでおり、
パート・派遣は低水準にあるものの、近年上昇傾向にある。
~略~
育児休業取得率について、
女性は8割台で推移している一方、
男性は上昇傾向にあるものの女性に比べ低い水準にある。
育児休業の取得期間は、
女性は9割以上が6か月以上である一方、
男性は徐々に取得期間が延びているものの、約4割が2週間未満であり、
依然として女性に比べて短期間の取得が多い。
~略~
6歳未満の子どもがいる世帯で、
夫も妻も雇用されている場合の1日当たりの家事関連時間を比較すると、
2021(令和3)年において、
妻は6時間32分であるのに対して、
夫は1時間57分であり、
3.4倍の差がある。
しかし、近年、その差は縮小傾向にある。
~略~
正規雇用を希望しながらそれがかなわず非正規雇用で働く者(不本意非正規雇用労働者)の割合は、
年々減少しており、
2024(令和6)年においては、男女とも100万人を下回っている。
割合については、
2013(平成25)年に男性で30.6%、女性で14.1%であったが、
2024年には男性13.7%、女性6.5%である。
~略~
介護をしている者のうち、有業の者について見てみると、
2022(令和4)年には、15歳以上の人で介護をしている人は約629万人いるが、
そのうち58.0%が有業となっている。
近年、介護をしている者に占める有業者の割合は増加傾向にある。
~略~
年間総実労働時間を就業形態別にみると、
一般労働者はおおむね2,000時間台で推移していたが、
2019(令和元)年以降、2,000時間を下回っている。
また、パートタイム労働者は長期的に減少傾向で推移し、
2019年以降、1,000時間を下回っている。
~略~
2023(令和5)年の年次有給休暇の取得率は65.3%と、
前年より3.2ポイント上昇し、1984(昭和59)年以降、過去最高となった。
~略~
企業におけるテレワークの導入状況を見ると、
2020(令和2)年に急激に5割近くまで増加しており、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響がうかがわれる。
その後は約5割の水準で推移している
~略~
フリーランスは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされている。
総務省「就業構造基本調査」(2022(令和4)年)によると、
2022年において、本業がフリーランスの数は209万人となっており、
有業者に占める割合は3.1%となっている。
~略~
世帯構成の推移と見通しについて見てみると、
単身世帯、高齢者単身世帯 ともに、今後も増加が予想されている。
2050(令和32)年には、一般世帯に占める単身世帯は44.3%に達すると見込まれ、
5世帯に2世帯になると推計されている。
また、高齢者単身世帯は20.6%に達すると見込まれ、
5 世帯に1 世帯になると推計されている。
なお、「3世代世帯」の推移について見てみると、
1986(昭和61)年には世帯総数の15.3%であったが、
2023(令和5)年においては3.8%と大幅に減少している。
~略~
地域での付き合いについて見てみると、
「付き合っている」とする者の割合 が54.2%、
「付き合っていない」とする者の割合は44.0%である。
都市規模別に見ると、
「付き合っている」とする者の割合は小都市、町村で高く、
「付き合っていない」とする者の割合は大都市で高くなっている。
また、年齢別に見ると、
「付き合っている」とする者の割合は60代以上で高く、
「付き合っていない」とする者の割合は、特に若い世代で高くなっている。
特に大都市や若い世代の間では、地域の付き合いが特に希薄になっていることがうかが
える。
~略~
近年のデジタル化についても、人々の関わり方に大きな変化を与えていると考えられる。
例えば、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス。例:Facebook,LINE,Instagram,X
(旧Twitter)など)の利用状況について見てみると、
2023(令和5)年には、利用者は全体で8割を超える高い状況にある。
特に13~19歳、20代の若者では利用率が9割を超えており、
特に高い状況にある。
利用目的としては、「従来からの知人とのコミュニケーションのため」が一番多く、
人とのつながり方に変化を与えていると考えられる。
~略~
第2章 社会保障・労働施策に関する若者の意識と知ることの意義・・・P.54~
第1節 若者の社会保障・労働施策に関する意識
~略~
本章では、まず、高校生に対して行ったアンケート調査の結果などを通じ、
若者の社会保障や労働施策に対する考え方や、
社会保障教育や労働法教育の経験などについて見たあと、
前章の内容も踏まえ、若者が社会保障や労働施策を知ることの意義について考えていきたい。
~略~
社会保障制度や労働施策について関心があるかを聞いたところ、
「とても関心がある」「やや関心がある」を合わせた割合は、
医療が63.6%、年金が58.3%、介護が43.3%、
福祉が49.2%、公衆衛生が47.5%、
労働時間のきまりが79.5%、賃金のきまりが80.0%
であった。
~略~
社会保障制度や労働施策について、
具体的な制度などを示して理解しているかを聞いたところ、
「よく知っている」「何となく知っている」を合わせた割合については、
いずれも半数を超えており、
このうち、「病院で健康保険証(マイナンバーカード)を提示すると、医療保険が利用できるので、
自分で支払わなければならないのは一部(通常3割)である」
「生活するお金に困った場合、市区町村に相談すれば、様々な支援や生活保護を受けることができる場合がある」
「働く時間が一定時間を超えたら休憩がもらえる」については、
6割を超えていた。
~略~
アルバイトの経験の有無と、
社会保障制度や労働施策への関心度、理解度との関係を見てみると、
アルバイト経験がある人は労働施策の理解度が高く、
アルバイト経験のない人は労働施策の理解度が低い傾向がうかがえた。
~略~
「社会保障制度(医療、年金、介護、福祉、公衆衛生など)について、
学校の授業 で習ったことがある」(以下「社会保障教育の経験がある」という。)のは
65.3%であり、そのうち54.2%が授業の内容を覚えている。
また、「働くときのルール(労働時間や賃金などのきまり)など働くときに知っておくべきことについて、
学校の授業で習ったことがある」(以下「労働法教育の経験がある」という。)のは
62.7%であり、そのうち70.0%が授業の内容を覚えている。
~略~
「社会保障制度は、社会全体の支え合いの仕組みである」ことについて、
「よく知っている」「何となく知っている」を合わせた割合は53.3%だが、
社会保障教育の経験がある場合は63.4%となっており、
社会保障教育の経験がない場合の43.0%と比べて高くなっている。
社会保障教育の経験によって、社会保障の理念である
「社会保障制度は、社会全体の支え合いの仕組みである」ということへの理解が
促進される可能性があることが示唆される。
~略~
「社会保障制度や働くときのルールなどの知識を得るために今後利用したい手段」(複数回答)については、
「インターネット(HPなど)」が68.4%と一番多く、
「SNS」が56.5%、
「学校」が48.5%、
「家族・知人」が45.9%
と続いている。
~略~
「社会保障制度や働くときのルールなどの情報を入手するとしたら、
心配ごとや気になることはあるか」(複数回答)については、
「SNSなどの情報が正しいかどうかわからない」が54.9%と一番多く、
「どうやって情報を調べたらいいのかわからない」が32.1%、
「公的機関のホームページなどでどこに情報があるかわかりにくい」が25.8%、
「特に心配ごとや気になることはない」が25.0%
と続いている。
また、今後利用したい手段として
「インターネット(HPなど)」と「SNS」のどちらか又は両方を選択した人のうち、
「SNSなどの情報が正しいかどうかわからない」と回答した人は90.6%となっており、
情報の信頼性に疑問を抱きながらもこれらのツールを選択する状況が垣間見える。
~略~
第2節 社会保障や労働施策を知ることの意義・・・P.67~
kuma
本節は『特に読んで欲しい』という項目です。
事例とコラムがメインでした。
試験対策上の重要度が判別不能です。
気になる方は一読頂けたらと思います。
第3章 若者に社会保障や労働施策を知ってもらうための取組状況と方向性・・・P.93~
第1節 社会保障教育・労働法教育に関するこれまでの検討状況
『省略』
第2節 現場における取組状況
『省略』
第3節 今後の方向性
『省略』
おわりに
次世代の主役となる若者の皆さんに期待すること
社会保障や労働施策の役割やそれを知ることの意義について、理解していただけましたか?
この白書を読んでくださった皆さんに期待することがあります。
「社会保障や労働施策について、自分事として考えてほしい。」ということです。
具体的には、以下の2点です。
1. 将来、何か生活していく上で困ったことがあったとき、利用できる制度があること、
相談できる場所があることをしっかり覚えておいてください。
そして、相談することをためらわないでください。
困ったことがあったときに一人で解決する必要はありません。
2. 自分の周りに困っている人がいないか、気にしてみてください。
これは今からでもお願いしたいことです。
クラスメート、近所の人、自分の家族も含め、
あなたに関わっている人はたくさんいると思います。
困っている人がいても、あなた自身が一人の力で解決する必要はありません。
話を聞いてあげたり、利用できる制度があることや、
相談できる場所があることをさりげなく教えてあげたりするだけでも救われる人がいるはずです。
この厚生労働白書が、皆さんの将来に少しでも役立つものになっていることを願っています。
若者以外の皆さんにお願いしたいこと
今回の厚生労働白書は、若者が、
今後生きていくために必要になるだろう社会保障や労働施策について、
興味を持つきっかけや知る一助になればと思い、作成しました。
ぜひ、皆さんの周囲にいる若者や、若者と接する機会の多い学校の先生方などに向けて、
本白書の存在をお知らせいただけると幸いです。
~略~
(その1)まとめ
今回は、公開されている厚生労働白書(令和7年版)を、
社労士試験対策として、抜粋、編集しました。
文章と数字の情報量が多く、読むことが大変だったかと思います。
本記事を一読頂き、更に内容を深めたいという方は、
厚生労働省のHPより、本文を参照ください。
本記事参照:厚生労働省 統計情報・白書 令和7年版厚生労働白書
※白書の内容が多い為、1部と2部で記事をわけることにしました。
次回は後半の2部に続きます。
【関連記事】
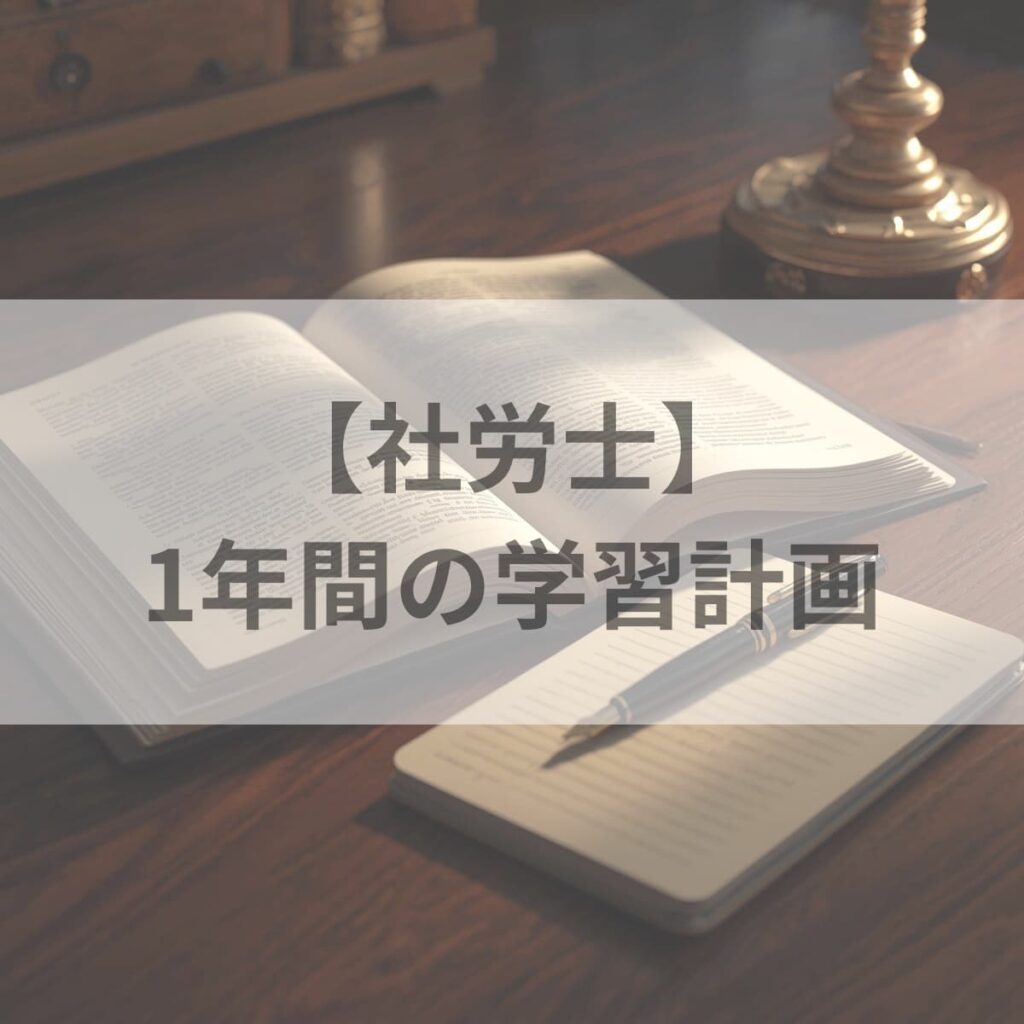
kuma