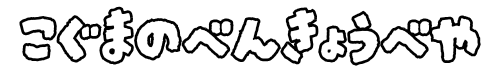最高裁第二小法廷 昭和56年(1981年) 9月18日
本記事の参照:裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/
主文
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
被上告人らの請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人木村憲正の上告理由第一点及び第二点、同酒巻弥三郎、同植松宏嘉、同青木一男の上告理由第一点及び第二点、同和田良一、同古賀野茂見、同青山周、同宇野美喜子の上告理由第一点ないし第三点について
一 原審の適法に確定した事実関係は次のとおりである。
(1) 被上告人らを選定した原判決別紙目録(一)記載の選定者ら(以下「被上告人ら」という。)は、
上告会社のD造船所に勤務する従業員であり、
E労働組合(昭和四五年九月一三日結成、以下「E労組」という。)に所属する組合員である。
(2) E労組が昭和四七年七月及び八月の両月にわたつて行つたストライキに際して、
上告会社は、被上告人らに対して、各ストライキ期間に応じた家族手当を所定の賃金支払日である
同年七月及び八月の各二〇日に支払わず、これを削減した。
(3) この家族手当は、上告会社の就業規則の一部である社員賃金規則一八条(昭和四七年六月改正のもの。)
により、扶養家族数に応じて毎月支給されていたものである。
(4) D造船所においては、昭和二三年頃から昭和四四年一一月まで、
就業規則の一部である社員賃金規則中に、ストライキ期間中、
その期間に応じて家族手当を含む時間割賃金を削減する旨の規定を置き、
右規定に基づいてストライキ期間に応じた家族手当の削減をしてきた。
(5) そして上告会社は昭和四四年一一月一日賃金規則から家族手当削減の規定を削除し、
その頃作成した社員賃金規則細部取扱(以下「細部取扱」という。)のなかに同様の規定を設けたが、
この作成に当たつて、上告会社従業員の過半数で組織されたF労働組合の了承を取りつけた模様である
(なお、E労組は、前記のとおり昭和四五年九月に結成されたのであつて、この当時は存在しなかつた。)。
(6) 上告会社は、この改正後も、昭和四九年家族手当が廃止され、
有扶手当が新設されるまで、従来どおり、ストライキの場合の家族手当の削減を継続してきた。
(7) なお、E労組は、昭和四七年八月一七日、上告会社に対し、家族手当削減分の返済を申入れた。
原審は、以上のような事実を認定しながら、家族手当の削減が労働慣行として成立し、
それがすでに被上告人らとの労働契約の内容となつているものとは認めえないとし、
本件の場合に家族手当を削減することは、労働基準法三七条二項及び
本件賃金規則二五条の規定の趣旨に照らしても著しく不合理であるから、
このような不合理な労働条件は、
たとえ会社側が一方的に家族手当の削減を継続してきた事実があつても、
これによつて適法かつ有効な事実上の慣行として是認することはできない、と判断している。
しかしながら、原審の認定した事実関係によれば、上告会社のD造船所においては、
ストライキの場合における家族手当の削減が昭和二三年頃から昭和四四年一〇月までは
就業規則(賃金規則)の規定に基づいて実施されており、その取扱いは、
同年一一月賃金規則から右規定が削除されてからも、細部取扱のうちに定められ、
上告会社従業員の過半数で組織されたF労働組合の意見を徴しており、
その後も同様の取扱いが引続き異議なく行われてきたというのであるから、
ストライキの場合における家族手当の削減は、
上告会社と被上告人らの所属するE労組との間の労働慣行となつていたものと
推認することができるというべきである。
また、右労働慣行は、家族手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入しないと定めた
労働基準法三七条二項及び本件賃金規則二五条の趣旨に照らして
著しく不合理であると認めることもできない。
これと異なる見解に立つて本件家族手当の削減を違法とした原判決は、
法令の解釈適用を誤つたものというべきであつて、
右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、
論旨は理由があり、原判決は、その余の点につき判断するまでもなく破棄を免れず、
更にこれと同旨の第一審判決は取消を免れない。
二 そこで進んで、原審が確定した事実に基づき被上告人らの請求の当否について判断する。
まず、被上告人らは、本件家族手当は賃金中生活保障部分に該当し、
労働の対価としての交換的部分には該当しないのでストライキ期間中といえども
賃金削減の対象とすることができない部分である、と主張する。
しかし、ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及び
その部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、
当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とし、
上告会社のD造船所においては、昭和四四年一一月以降も本件家族手当の削減が
労働慣行として成立していると判断できることは前述したとおりであるから、
いわゆる抽象的一般的賃金二分論を前提とする被上告人らの主張は、
その前提を欠き、失当である。
所論引用の判例(最高裁昭和三七年(オ)第一四五二号同四〇年二月五日第二小法廷判決、民集一九巻一号五二頁)は事案を異にし、本件に適切でない。
次に被上告人らは、本件家族手当の削減は、
(1) 労働基準法三七条二項が割増賃金算定の基礎に家族手当を算入しないとする法意並びに、
(2) 同法二四条の規定にも違反する、と主張する。
しかし、同法三七条二項が家族手当を割増賃金算定の基礎から除外すべきものと定めたのは、
家族手当が労働者の個人的事情に基づいて支給される性格の賃金であつて、
これを割増賃金の基礎となる賃金に算入させることを原則とすることが
かえつて不適切な結果を生ずるおそれのあることを配慮したものであり、
労働との直接の結びつきが薄いからといつて、
その故にストライキの場合における家族手当の削減を直ちに違法とする趣旨までを含むものではなく、
また、同法二四条所定の賃金全額払の原則は、
ストライキに伴う賃金削減の当否の判断とは何ら関係がないから、被上告人らの右主張も採用できない。
そうすると、上告会社のした本件家族手当の削減は違法、無効であるとはいえず、
被上告人らの各請求はいずれも理由がないから、棄却を免れない。
よつて、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六条、九三条、八九条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
キーワード
ストライキ。就業規則。家族手当。労働慣行。
kuma